【完全版】剣道の足さばき:送り足・踏み込みまで”速く・強く・崩れない”を身につける
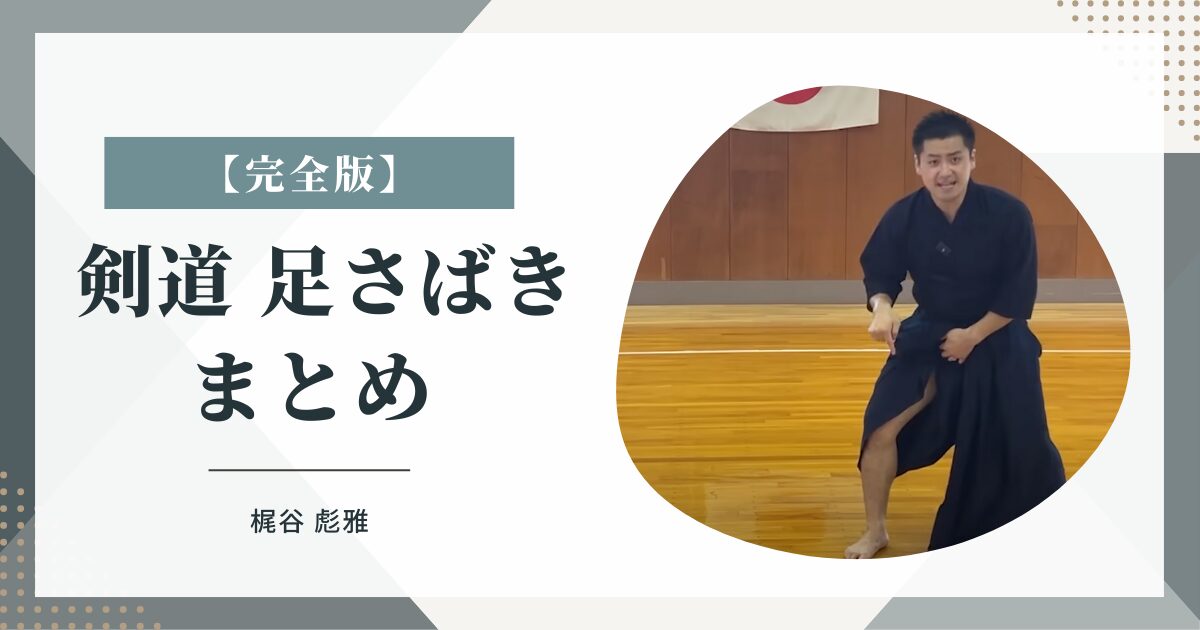
技が出ないのは“手”ではなく“足”。
面が届かない、足が止まって打たれてしまう———その多くは足さばき(足捌き)原因です。
剣道は「一眼二足三胆四力」。
本記事は、送り足・開き足・継ぎ足・歩み足・踏み込み、足捌きに関わる事を解説していきます!
なぜ剣道において足さばきが最も重要なのか
剣道を始めたばかりの方も、長年稽古を積んでいる方も、一度は「もっと速く打ちたい」「美しい技を決めたい」と思ったことがあるでしょう。
しかし、多くの剣道家が見落としがちな真実があります。
剣道において足さばきは、単なる移動手段ではありません。足さばきは剣道のすべてを支える土台であり、以下の3つの重要な役割を担っています。
- 打突前の足捌き
- 間合いの攻防としての足さばき
- 足捌きが生涯剣道に繋がる
打突前の足捌き
面・小手・胴・突きのすべての技は「足 → 体 → 手」の順序で生まれます。
どれほど手先の技術を磨いても、足の準備ができていなければ、その技は相手に届きません。
美しい技は、美しい足さばきから始まります。
間合いの攻防としての足さばき
剣道における間合いの制御は、すべて足で決まります。
相手に技を届かせる、相手の攻撃を捌く、相手を誘い込む—これらの高度な戦術はすべて、精密な足さばきによって実現されます。
足捌きが生涯剣道に繋がる
静かでムダのない足さばきは、体への衝撃を最小限に抑え、長時間の稽古や試合の終盤でも安定した一足一刀の間合いを維持できます。
また、ただ動かすのではなく『重要な場面で足が動く』ということが非常に大切です。
高段者の先生で強いと思う先生は、重要な場面で居付かきません。
起こりを捉えたり、間合いを切ったり、無駄の無い足捌きが非常に上手いと思います。
正しい足捌きを習得する事が剣道を続けるための投資にも繋がります。
基本理論:一眼二足三胆四力が教える足の役割
剣道には「一眼二足三胆四力」という古くからの教えがあります。
この教えが示すように、足は「眼」の次に重要な要素として位置づけられています。
- 一眼:相手の心や体の動きを察知し、洞察する力
- 二足:技の基本となる足さばき
- 三胆:強い気持ち、決断力、忍耐力、気力、意志力、持久力
- 四力:技を実際に出すための身体能力や技術
この順序が示すように、目の次に重要なのが足です。
気持ちや技術面の強化も勿論ですが、何よりも先に強化すべきなのが『足の強化』です。

崩れない土台作り:姿勢と重心の基本
美しい足さばきの前提として、正しい姿勢と重心の配置があります。
多くの剣道家が見落としがちですが、これらの基本が足さばきの質を決定します。
足幅と足の向き
- 足幅:肩幅程度(個人差あり)
- 前足:まっすぐから軽く内向き
- 後足:左足も真っ直ぐが理想
- 左踵:理想:1〜2cm浮かせる
私:5cmくらい空いてる気がする。 - 右踵:数ミリ浮かせる(踵に重心はNG)
足幅や構えの足は人それぞれです。
年代や剣風によっても変わります。
なので、基本をベースに自分に適した足幅を見つけましょう!
重心の位置
重心は『拇指球』『親指の付け根』 の足の内側に重心をかける意識が重要です。
外側に重心がかかってしまうと、蹴り出しの時に前に重心を移すことができず手打ちになってしまいます。
手打ちになると打突も軽くなってしまうので注意が必要です。

代表的な足さばき:特徴と実戦での使い分け
剣道の足さばきは、それぞれ明確な目的と使い分けがあります。
以下に主要な足さばきの要点とよくある間違いをまとめました。
| 種類 | 主な用途 | 重要なポイント |
|---|---|---|
| 送り足(すり足) | 基本移動・間合い詰め | 母指球 右足に重心が乗りすぎない |
| 歩み足 | 胴技の後 抜き胴・返し胴・引き逆胴など | 打突後に使うことが多い。 間合いの攻防で使うと相手にバレやすい |
| 継ぎ足 (上級編) | 微調整・誘い 間合いを盗む | 無意識で使わないこと。 意図的に誘いや間合いの盗みで使えるなら上級者 |
| 踏み込み足 | 打突する時 | 大きな音であるほど良い。 踏み込もうとしない。重心を乗せる感覚 |
送り足(すり足):剣道の標準ギア
送り足は剣道における最も基本的な移動方法です
「剣道の基本」と呼ばれるように、この基本の足捌き習得が打突や相手の技を捌くための土台となります。
基本手順
- 左足で腰を送り出す
- 右膝を出す感覚
- 右足に重心が乗る瞬間に左足を引き付け
- 引き付けと同時に左足に重心を乗せ替える
この4つの手順を繰り返す事で送り足習得ができます。
ポイントは2番の右膝を出す感覚で、右足のつま先を出したとしても重心が乗り切るのは、必ず右膝の下に足がきます。
つま先より手前に膝があると、踏み込みが遅れる、かつ戻り足の踏み込みになるので、膝を出す感覚がおすすめです。
足捌きの基本は動画で解説しています。
指導のポイント
初心者に指導するときは、止まる動作から意識させることが重要です。
- 右足を出して止まる
- 左足の引き付けと同時に右足を浮かせる
(右足を浮かせると左足に重心が乗る) - また左足で右足を前に送る
①〜③を繰り返す。
このようにまずは1回1回止まる動作で練習することが意識練習に繋がります。
できるようになってきたら、大きな動作ではなく、小さな動きで速さを身につけれるようにしましょう。
足音ゼロの足捌き練習や上下運動を消す足捌き練習も効果的です。
上下運動をなくすための練習はこちら
足捌き:後退(後ろに捌く)
前に行く足捌きができるようになったら次は、後ろに下がる足さばきを練習していきます。
前に行く時は、左足で右足を送り出す。
そして左足を引きつける瞬間に右足を浮かせる。
逆に後ろに行く時は、右足で後ろに体を押し出し、左足に重心が乗る瞬間に左足を浮かせる感覚で練習していきます。
実戦的な足さばき:開き足・歩み足・継ぎ足・踏み込み足
開き足:角度を作る技術
使用場面:中心をずらして小手面や斜めの面を狙う時。
開き足での『左に開いて入る方法』を誘いに使うこともできます。
重要なコツ:つま先を相手に向けたまま開くことです。多くの人が間違えるのは、つま先も一緒に外へ向けてしまうこと。
これでは中心を完全に外してしまい、相手に隙を与えます。
歩み足:胴技で超重要
使用場面:胴技の後、抜き胴・返し胴・引き逆胴など。打突後に使うことが多いです。
重要なコツ:間合いの攻防で使うと相手にバレやすいです。
伝え方は良くないかもしれませんが、打突後に『走る』というイメージの方が近いかもしれません。
ただ、体の向きなどに注意する必要があります。
次の動画で引き逆胴や、引き胴の足捌きとして使っています。
動画でチェック
抜き胴や飛び込み胴の時の練習方法についても次の動画でまとめています。
基礎練習から実践練習動画はこちら
継ぎ足:精密な間合い調整&誘い
使用場面:相手が下がる瞬間(攻め勝った時)
重要なコツ:無意識で使わないこと。
意図的に誘いや間合いの盗みで使えるなら上級者
次足は基本的にはやらないことをお勧めします。継ぎ足が悪いわけではなくて、継ぎ足によって相手に起こりがバレてしまうことが問題です。
継ぎ足をする事で間合いを盗む事もできるので、より遠くに打つ事ができます。
攻めを生かした伸びる面打ちを習得したい人は練習してみてください!
全日本選手権や世界大会団体で優勝されている松崎選手が松﨑 賢士郎(まつざき けんしろう)選手が非常に上手い面打ちを使います。
具体的な面打ちについては次の記事を参考

踏み込み足:1本にするために超重要
使用場面:面技・小手技・引き面・引き小手・引き胴、基本技のほとんどが踏み込みが必要です。
重要なコツ:踵とつま先の間で踏み込みことが重要です。
踵だけだと→ドン!という音になる。
つま先だけだと→パン!という音になる。
「ドン!」と「パン!」の間の音を意識して踏み込むことが重要です
踏み込みの動画はこちら

円の足捌き
基本的な前に行く、足捌きと後ろに行く足捌きが慣れてきたら、前後の足捌きの練習がお勧めです。
円の足さばきをやるべき理由
剣道を始めたばかりの時に、すり足で常に動き続ける感覚がないと思います。
勢いで打ってしまったり、足が止まっている所を打たれてしまう事も多いでしょう。
そこで足で攻める感覚、足で相手の攻撃を捌く感覚を身につける事で実践的な足捌きを身につけることが可能です。
円の足さばき:具体的練習方法
重要なポイントは
前に行く瞬間&後ろに行く瞬間が重要
円の足捌きをする時に一定のスピードで練習してしまいがちですが、蹴り出しの筋力強化をする事でより実践で使える足捌きになります。
具体的な円の足さばき練習方法については下記の動画を参考にしてみてください。
円の足捌きの練習方法はこちら(解説付き)
円の足捌き(練習特化動画)
よくある悩み・間違いと即効対策
足が捌きが遅い理由
原因:動きが大きすぎる。地面を蹴る感覚がない。
対策:円の足捌きで足の動き幅をできるだけ小さく意識する。動き幅については意識改善しかありません。
蹴る感覚が無い人は、ケンケンで前に行く練習をしたり、ケンケンで後ろに移動する練習をしてみてください。
片足で蹴ることで蹴る感覚や力が身についてくれば、足捌きの中でも蹴る感覚を掴めるようになってきます。
距離感がずれる場合
原因:練習不足。(厳しい伝え方でごめんなさい)
距離感に関しては、一番難しいポイントです。
理由は『相手によって変わるから』です。
- 前に来る相手
- その場で避ける相手
- 下がる相手
- これらを全て使う相手
絶対的な正解は無いですが、感覚的正解に近づけることがで重要です。
そのためには、間合いを掴む感覚練習が必要になります。
間合いの感覚を掴むための練習は動画で参考にしてみてください。
小学生に間合いの感覚と足で捌く練習方法
トップ選手・指導者の共通点
私が多くのトップ選手を指導・観察してきた中で気づいた共通点があります。
試合重視の足捌きと、昇段審査の時の足捌きは違うということです。
これは、八段でもあり世界大会、全日本選手権でも優勝されている先生から聞いた話ですが、JAPAN合宿の選手と稽古をする時と八段の先生との立ち会いは重心の意識も足幅も違うと言っていました。
昇段審査・立ち会いの足捌き
剣道の基本の足捌きは『左足重心』が基本です。
足幅も指導方法は沢山ありますが、その人の肩幅ぐらいで、右足の踵と左足の爪先とが同一線上。や横の足幅は肩幅程度など言われます。
先ほどの先生もまさに立ち会いの時はこのような基本の足捌きを意識するとの事でした。
試合の足さばき
しかし、JAPANの選手と地稽古するときに基本通り左足に重心を乗せると反応が遅れてしまい、足が居着いてしまうそうです。
試合の時は、左足より右足の方に重心をかける。
そして、足幅に関しては反応スピード重視で、前にも飛べる、相手が来た瞬間に後ろに蹴れる状態にしておくそうです。
基本の足捌きだと、左足に重心が乗っているので前にはしっかり飛べるが、後ろに行くためにもう一度右足に重心を乗せ替えないといけないので捌きの難易度が上がります。
基本と試合の足さばきを使い分ける
まずは『基本の足捌き』を習得する。
その後『試合の足捌き』を習得する。
順序で言えば、このようにも言えますが、私の場合は基本の練習もしっかりやる、試合の練習も一緒に稽古する。
これが一番いいのでは無いかと考えます。
理由としては、高段位になってから試合に出るのではなく、試合にも出ながら昇段審査が間に入ってくると思います。
剣道の足捌き:重要ポイントまとめ
今日から始める足さばき改革
剣道の技が出ないのは”手”ではなく”足”。面が届かない、足が止まって打たれてしまう———その多くは足さばき(足捌き)が原因です。
重要なポイント:
- 一眼二足三胆四力:目の次に重要なのが足
- 「足 → 体 → 手」の順序で技は生まれる
- 重心は拇指球(親指の付け根)に意識
- 無意識の継ぎ足は禁物、意図的に使えれば上級者
段階別アプローチ
初心者:送り足の基本習得(止まる動作から始める)
中級者:各種足さばきの使い分け習得
上級者:試合用と審査用の足さばき使い分け
継続のための合言葉
「重要な場面で足が動く」
高段者の先生で強いと思う方は、重要な場面で居付きません。
起こりを捉えたり、間合いを切ったり、無駄のない足さばきが非常に上手です。
正しい足さばきを習得することは、生涯剣道を続けるための投資でもあります。
最後に
足さばきは一朝一夕では身につきません。しかし、正しい理論と継続的な練習により、必ず上達します。
技術の向上だけでなく、怪我の予防、生涯にわたる剣道の継続のためにも、今日から足さばきの見直しを始めてみてください。
あなたの剣道が変わる第一歩は、足さばきから始まります。
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?










