【徹底解説】剣道で重心移動を極める!打突力が劇的に変わる方法5ステップ
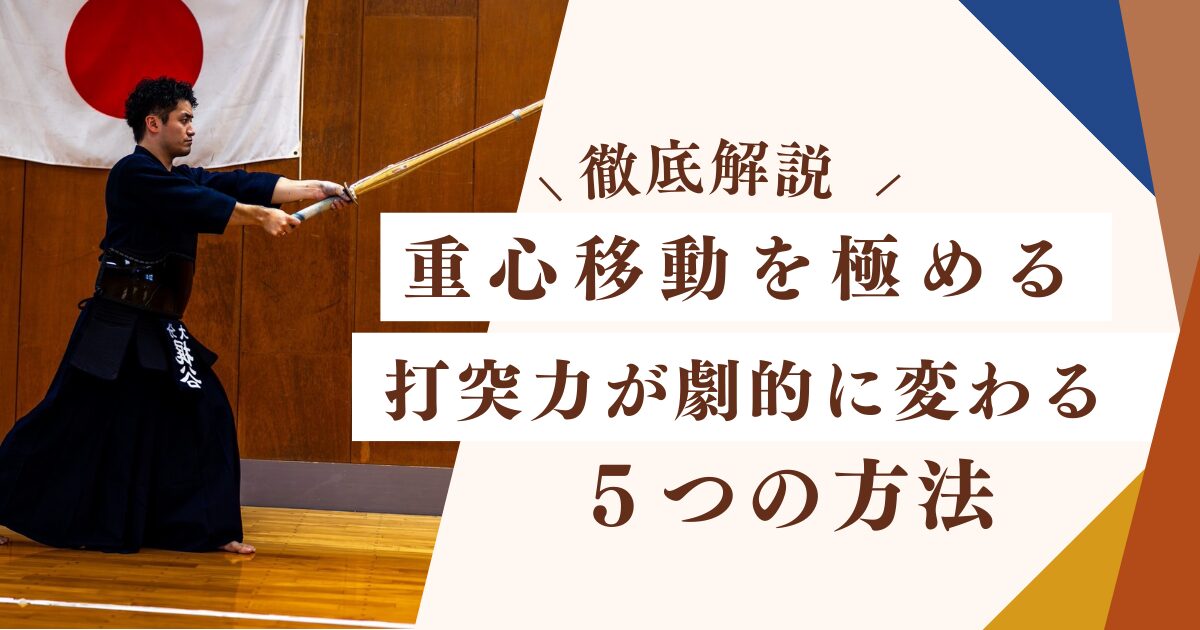
剣道の重心移動――
「着地の瞬間」に合わせれば、打突は変わる
こんにちは、梶谷彪雅です。
「振っているのに軽い」「当たっているのに一本にならない」——この相談、レッスンで本当に多いです。
結論はシンプル。重心が上で止まったまま当てていることが原因であるケースがほとんど。
本記事では、重心が“下りてくる瞬間”に打突を一致させるための考え方と稽古方法を、前技(面・小手・胴)/引き技まで丁寧に解説します。
読み終える頃には次の状態を目指せます。
- 一本性が上がる:当たりと体の収束が合い、審判に伝わる
- 切れが増す:短い接地時間と前方向の流れで、残心まで崩れない
- すぐ実践できる:道場でそのまま使える確認稽古と1週間プランつき

※本稿は重心移動に特化しています。踏み込みのやり方や接地の作り方(音・母指球など)は別記事で詳しく解説しています → 踏み込みの完全ガイド。
また、送り足・継ぎ足・開き足などの足捌きの型は必要に応じてこちらへ → 足捌きの完全ガイド
なぜ踏み込み力が剣道で最強なのか?
2024年全日本剣道選手権大会で優勝した選手の試合を分析していく中で、一つの重要な真実に辿り着きました。
“剣道で一本を決める踏み込み力の極意と重心移動の秘訣”こそが、現代剣道で勝利を掴む鍵となっているのです。
全日本選手権クラスのスピードは圧倒的で、全てを肉眼で捉えることは困難です。
そんな中でも一本として認められる技には、共通する要素があります。それが踏み込みの力強さなのです。踏み込み力が一本を決める3つの理由
- 打突音の迫力 – 軽い打突でも大きな踏み込み音が会場に響き渡る
- 技の説得力 – 当たっていなくても一本に見せる力
- 審判への印象 – 迷った時に旗を上げさせる決定力
重心移動とは何か(本稿のスタンス)
本記事で扱う重心移動は、「足をどう出すか」よりも**“体の重さの流れ”をどこで打突に重ねるか**というテーマです。
- 踏み込みの形(音・母指球・左足の引きつけ等)=別記事:踏み込みの完全ガイド
- 足捌きの型(送り足・継ぎ足・開き足の角度や幅)=別記事:足捌きの完全ガイド
ここでは、**どの技にも共通する“重さの置き場所とタイミング”**を身につけます。
重心移動で着地の瞬間を理解する
理想の打突は、
- 体がわずかに浮いた直後に重心が下がってくる。
- 下りる瞬間に踏み込み。同時に当たり(竹刀の衝突)が来る。
- その直後、体が前へ抜ける(止まらない)
打突後右足の力が重要。
ポイントは重心が浮いてる時に打突をしないこと。
浮いた状態で手だけが先行すると、どれだけ強く振っても軽く見えます。
逆に重心が下りる瞬間に合わせると、同じ力でも打突の実効と見え方が跳ね上がります。
重心移動での前技への落とし込み(面・小手)
前に出る技でも理屈は同じです。打突の直前でわずかに体が浮き、下がってくる瞬間に当てる。
少しだけ面技と小手技の意識が違うので解説していきます。
面
実際に技を打つときの意識ポイントは『遠くに飛ぼうとしないこと』です。
遠くに飛ぼうとすると、通常より上に浮いてしまいます。そうすると着地までが遅くなるので、相手に避けられてしまいます。
面技には
- 出鼻面
- 攻め勝って打つ面
の2つがあるので、面技によっても重心移動のやり方は変わってきます。
面技については次の記事も参考にしてみてください。

小手
小手技に関しては、飛ぶというより『斜め下に落とすだけ』というイメージが近いです。
応用技の面フェイント小手など、重心を浮かすことで、相手の手元を浮かせる技もあります。
実践的な小手うちは動画で解説
重心移動:引き技への落とし込み(引き面・引き小手・引き胴)
引き技でよくある失敗は、下がりながら当てていること。これだと重心が落ち切らないため強い踏み込みや打突はできません。
正解は、その場で重心を落とす。→その瞬間に当てる→後方へ下がるの順です。
引き面の重心の乗せ方はこちら
引き技は重心を落とすだけなので簡単ですが、下りながら打突してしまう人が多く、失敗しやすいのでより練習が必要です。
踏み込みの音や練習方法があっているかどうかを確認するために『試合分析・稽古分析』を梶谷彪雅に依頼してみましょう!
道場ですぐできる確認稽古
ここからは実際に体へ入れる時間です。
完全初心者用に手順はやさしく。各10〜20本を目安にどうぞ。
楽に感じる人は回数を増やすなり、梶谷彪雅にさらに上級編を聞いてみてください!
その場・重心落としの面練習(レベル★)
軽く体を浮かせ(ジャンプ)して、重心が落ちる瞬間に面。
ねらい:重心を落とす練習、イメージを沸かせる。
最短間合いの面(レベル★)
一足一刀の間合いより近い間合いから、ジャンプして重心を意識しながら、通常の面打ち。
ねらい:重心移動を上下から、前に移動させる感覚を掴む。
私はこれをウォーミングアップの時に意識練習として活用しています。
試合前に少しだけ重心移動練習してました
引き面:下げて→当てて→抜く(レベル★★)
小さく浮く→着地と同時に面→後方へ下がる。
ねらい:下がりながら当てない。
引き面はこちらの動画が一番わかりやすい
踏み込みの音や接地を深掘りしたい場合は、重心移動の理解がつかめた後に → 踏み込みの完全ガイド
重心移動でのつまずきの原因と直し方
重心移動が理解できない
重心移動練習で一番困るのが、
これって重心移動できてるのかな?
とイメージが湧きにくい、あってるかどうかが分からないことだと思います。
これは客観的に見たとしても重心移動が完璧にできているかどうかを見分けるのも分かりにくいです。
重心移動が無意識にできている人もいます。
そういう人に教えて頂くと、言語化できていなくて分かりにくい場合があります。
私も直接指導する時に重心移動はの指導は意外と困ります。
その中で一番伝わりやすい方法がジャンプなので、ジャンプの着地の瞬間に重心を合わせる練習を必ずしてもらいます。
そうすると比較的、習得しやすいのでやってみてください。わからない人は僕に上位メンバーで直接聞いてください。
手足がバラバラ
原因: タイミングの同調不足
解決策:
- ゆっくりとした動作で同調性を確認
- 「足→腰→手」の順番を意識
- 打ち込み台を使って確認
- 意識的に手と足を合わせる練習
手と足が合わないことで悩まれる選手も多いと思います。
その多くの選手が無意識に打突をしていることが多いです。
なので、意識的に練習をする。意識練習が完璧になるまで無意識練習はしないほうがいいです。
無意識で手と足が合わない状態が続くと、それが癖になって、修正するのにものすごく時間がかかります。
まずはゆっくりでもいいので意識練習に取り組みましょう。

7. 下半身の安全な強化(ケガ予防)
重心移動を習得する上で、下半身の受け皿が大切です。踏み込みはかなり強い力が足に加わります。
無理のない範囲で下半身強化もしていきましょう。
- 自重スクワット:20〜30回×2(背中はニュートラル)
- 小さめジャンプスクワット:10回×2(膝とつま先は同方向)
- ふくらはぎのエキセントリック:台の縁でゆっくり下ろす10回×2
- 前脛骨筋のほぐしと下腿ストレッチ:稽古前後に各1〜2分
- 負荷は週10〜20%の漸増/違和感が出たら即ストップ
下半身トレーニングについては動画にもしているので参考にしてみてください。
下半身トレーニング初級編
下半身トレーニング上級編
下半身トレーニング自宅編
動画セルフチェックで重心移動を習得
スマホで横から撮るだけで、改善速度が段違いに上がります。見るのは3点だけ。
- 落ちる瞬間に踏み込んでいるか
- 音の大きさ(足だけで踏み込む場合と比べる)
まずはこの2つを動画で重心移動ができているかチェックしてみましょう。
ある程度できてきたらステップ1から順に練習していきましょう。
- ステップ1はジャンプからその場で
- ステップ2は前に重心移動をする練習
- ステップ3は実際の打突練習で
- ステップ4は面をつけてもできるか
- ステップ5は地稽古や試合で使える
よくある質問(FAQ)
Q. 音は大きいほど良い?
A. はい。重心移動ができていると、自然と体重が足に乗るので、大きな踏み込み音が鳴ります。
音の作りは踏み込み記事で深掘りを → 踏み込みの完全ガイド
Q. 前へ出ると動きが流れて軽くなります。
A. 再度その場の練習から。ステップ1から繰り返し練習しましょう。
Q. 開き足になってしまいます。。
A. 開き足は意識練習が必要です。必要に応じて開き足の基礎を復習 → 足捌きの完全ガイド

まとめ:剣道の重心移動で完璧な1本に
結局のところ、重心が下りてくる瞬間に当たりを置けるかどうかで、打突の“見え方”と“実効”は大きく変わります。
前に出る技でも引き技でも、やることは同じ——浮いている時に当てない。
この点が、一本性・切れ・残心までの流れを底上げします。
今日からの最短ルートを置いておきます。難しい理屈はここでおしまい。あとは稽古場で、体に落とし込むだけです。
- ステップ1はジャンプからその場で
- ステップ2は前に重心移動をする練習
- ステップ3は実際の打突練習で
- ステップ4は面をつけてもできるか
- ステップ5は地稽古や試合で使えるように
稽古の最後にスマホで横から10秒だけ撮影して、次の2つだけ確認してください。
- 落ちる瞬間に踏み込んでいるか
- 音の大きさ(足だけで踏み込む場合と比べる)
もし足運びや角度作りが不安なら、必要なときにだけ足捌きの基礎を復習してください(送り足/開き足の要点)→ 足捌きの完全ガイド。
また、接地の作り方や音の整え方を深めたい段階に来たら、重心移動の感覚を崩さない範囲でこちらへ進みましょう → 踏み込みの完全ガイド。
最後にひと言。
「重心が落ちる瞬間に打突する」——この合言葉だけを持って、次の稽古に入ってください。
続ければ、軽い打突も1本に見えます。重心が乗っていれば打突も強くなります。
あなたの打突は“一本に見える”だけでなく、“一本として通る”形に近づきます。
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?










