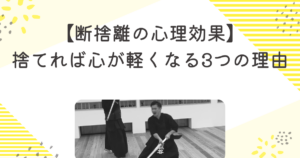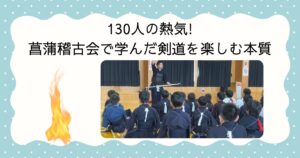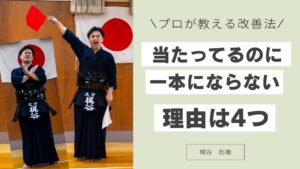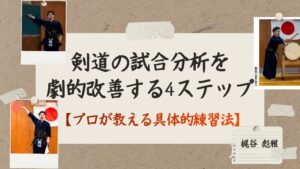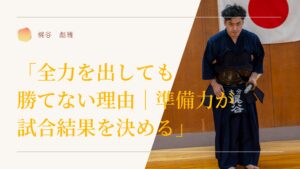あなたに合うのはどっち?大規模講演会vs小規模稽古会の選び方



剣道の稽古会、大規模と小規模どっちに行く?
あなたは今、こんな風に悩んでいませんか?
「稽古会に参加したいけど、人数が多い講演会と少人数の稽古会、どっちがいいんだろう?」
僕はこれまで200人を超える大規模な講演会から、10人程度の少人数制の稽古会まで、いろんな規模の稽古会を経験してきました。
直近では彪進会で20人や30人の稽古会があったり、今後は100人を超えるような講演会も予定しています。
今日はその違いについてお話しします。
どっちに参加したいのか基準を持っていただくと、自分に合った稽古会を選べるようになります。
小規模稽古会(彪進会)の特徴と学び
少人数だからできる「深い技術研究」
彪進会は、本気で強くなりたい人、強くなるための考え方を知りたい人が集まる稽古会です。
もちろん技術的にまだまだ足りないけれども、これから頑張っていきたいという人も大歓迎です。
ちょっときついこともやりますので、きつい時は無理せず見学でも全然OKです。
できるところまで挑戦してみて、無理だったら休む。この方法でも僕はいいと思っています。
その中で「こういった練習があるんだな」「俺全然体力ついていけないや」っていうのも気づきとしてあっていいと思うんですよね。
そこから「足りないから持ち帰って、次の稽古会までに努力するんだ」という目標を立てて今後の稽古に生かす。
これほどいい学びはないと思うんです。
少しきつい稽古もあれば、しっかりと技の研究もあります。
引き技を打つ時はこういう風に打つっていうのは大規模講演会でも伝えますが、打つ前の作りはもっとこうした方がいいよねみたいな深いところの研究も彪進会では行っています。
例えば引き技の時の左右の動き。
だいたい前後だけだったり、引き技を打つまでの動作を伝えることは多いんですけれども、打つ前の動作を伝えることってあんまりないじゃないですか。
僕はバスケットボールやラグビーのイメージで、右に行こうとして左に行ったり、左に行こうとして右に行くことによって、相手の視線が半歩遅れる状態を作り出す。
そうすればより打ちやすいなって思ったんです。
そういったところを伝えたり、実際にやってみたりしています。
一人一人に向き合える「個別指導」の価値
小規模稽古会では、休憩の間に一人一人に声かけさせていただいたりしています。
地稽古もできるだけみんなとやるために、20人の時は全員でやりました。
30人になってくると全員とやるのは時間的に難しくなってきますが、全員とできるのが一番いいかなって思っています。
前回もそうだったんですけど、2人一組でぐるぐる回って20回稽古をやるんですよ。
それだけでも結構しんどいと思うんですよね。
なのでそこも休憩してもちろんOKです。
でもみんなとできるだけ稽古をやるっていう意味では、そういった形をとっています。
全員と稽古できる「密度の濃さ」
大規模講演会になると、全員2人一組になって地稽古っていうのはなかなか難しいんですよ。
幅もなかなか取れないですし。
なのでがっつり地稽古もできる、しっかりと技の練習もできる、質問も全然やっちゃってOK。
これが少人数制ならではの稽古会かなと思っています。
大規模講演会の特徴と学び
講演形式で学ぶ「剣道の考え方」
大規模講演会では、基本的には僕が質問タイムを設けたり、「こういったことを意識して稽古していきましょうね」という講演時間があります。
彪進会の時はないですね。ほとんど質疑応答の時に個別で質問を受けるので、基本的には稽古にフォーカスしてやっていく感じです。
でも大規模講演会の時は、そういった時間を設けておかないと、一人だけにめちゃめちゃ質問責めされて他の人は回答できないってなったら困りますよね。
それだったら少人数制でいいじゃんってなっちゃうので、基本的にはそういったことはあまりやっていません。
稽古メニューに関しても、やっぱり大規模講演会になると大人数向けの内容になることが多いです。
例えば足さばきやったり、2人一組、入らなければ3人一組、それでも入らなければ4人一組という形でやっています。
なので必然的にやる回数が減ってしまうっていうのはちょっと理解していただきたいなと思います。
他の人のアドバイスから学ぶ「観察力」
100人200人の2人一組になってってなったら、めちゃめちゃ時間かかります。
特に小学生や中学生で「どうすればいいんだろう」っていう子たちが多いと、なかなかすぐ準備できないんで、まずここで時間がかかりますよ。
だいたい100人規模になってくると、2人一組になって一回座ってもらいます。
友達がいたら一緒に座れるので。3人一組になったら座る。
その全員が座るまでに結構時間かかるんですけど、座らせなかったら10分20分余裕でかかっちゃうんです。
できるだけ早くするために、そういった方法を取らせていただいております。
ここでもできるだけ皆さんにいろんなことやっていただきたいので技の練習をしていくんですが、やっぱり一人一人にアドバイスができない。
これが大規模講演会の一番の特徴かなと僕は思っています。
小規模だったら20人30人だったら一人一人に「こうしてこうして」っていう風にアドバイスできます。
でも100人200人だったら、もうどこにアドバイスをすればいいのか難しいです。
なので一人「こういったところの特徴を見つけたな、もう少しこうした方がいいな」っていうのを何人かピックアップして5人くらいピックアップします。
「こういう人がいました、こういう人がいました」っていう形で、「もう少しこういったところを意識してみましょう」という感じでアドバイスをしていきます。
なのである意味いろいろな人の改善点を聞けるっていう感じですね。
聞いて自分の頭の中でしっかり考えて落とし込むことができれば、絶対に学びになります。
他の人のアドバイスを自分ごととして置き換えてできない人っていうのは、どんな稽古会に行っても、あるいは自分自身の道場の練習でも全然効果薄いと思ってます。
成長できにくいと思っているので、この「他の人の悪いところを自分自身に置き換えてしっかり意識してやる」。
これができる人はやらないといけないですけどね。
そういったことをやろうと思って来ていただくのでもいいかなと思っています。
いろんなタイプと稽古できる「幅の広さ」
大規模のいいところは、いろんなタイプとやれるっていうのが一番いいかなと思っています。
20人とかだったら20人の中でしかやれないんですけど、大規模になるともっと幅が広いですよね。
「こんな打ち方する人がいるんだ」「こういう人いるんだな」っていうのをいろいろ目で見ることができると思うんです。
例えば地稽古の時に、ちょっと強そうな人を見つけておいて「地稽古お願いします」みたいな感じのも全然ありだと思います。
もちろん小規模でもできるんですけど、その幅が広いっていうことですね、大規模になると。
なので自分の意識が高ければ高いほど切磋琢磨し合える。
こういった場所なかなかないですからね。
僕も中学校の時に、稽古会兼大会みたいなのに参加した時は、絶対にこいつに負けたくないっていう強いやつを見つけて、そいつに一番にかかるぐらいの気持ちでいました。
そういったことができるかなと思っています。

どちらに参加すべき?判断基準
がっつり強くなりたい人向け:小規模稽古会
小規模稽古会は、本気で強くなりたい人に向いています。
一人一人に目が届くので、個別のアドバイスがもらえます。
技の深い研究ができて、全員と稽古できるのも魅力です。
質問も遠慮なくできるので、わからないことをその場で解決できます。
幅広く学びたい人向け:大規模講演会
大規模講演会は、いろんなタイプの人と稽古したい人に向いています。
他の人へのアドバイスを聞いて、自分に置き換えて学ぶ力がある人には最高の環境です。
講演形式で剣道の考え方を学べるのも、大規模ならではの魅力ですね。
自分の目的に合わせて選ぶ
内容としてはどちらもかなりがっつりやります。
大規模でも小規模でも、自分の今まで学んできたことをできる限り皆さんに伝えることを意識してやっています。
どこの県だからとか忖度なしで伝えさせていただいていますので、安心してください。
あなたの目的に合わせて、参加する稽古会を選んでみてくださいね。
今日からあなたも、自分に合った稽古会を選んで、一歩踏み出してみませんか。
まとめ:自分に合った稽古会を選んで、一歩踏み出そう
- 小規模稽古会は密度が魅力。一人一人に向き合える個別指導で、技の深い研究ができる
- 大規模講演会は幅が魅力。いろんなタイプと稽古でき、他の人のアドバイスからも学べる
- どちらも学びがある。大切なのは自分の意識の高さと、学んだことを自分ごとに置き換える力
あなたはどちらの稽古会に参加したいですか?
まずは一歩踏み出して、新しい学びを体験してみてください。
今日の話が、あなたの剣道人生の一歩を後押しできたら嬉しいです。
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?