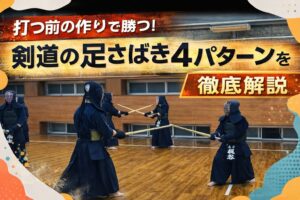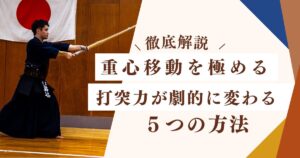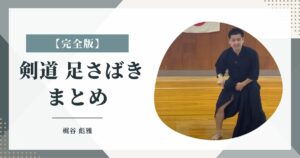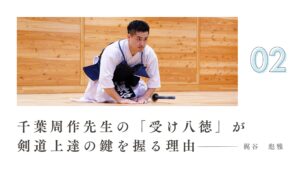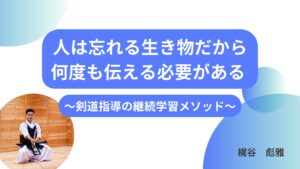剣道の切り返しで身につく10の効果|千葉周作の打ち込み十徳を現代解説



剣道の基礎を支える千葉周作の教え
今回は、いつもとは少し違った真面目な内容をお届けします。
剣道器具について語り、プロ剣道家として活動している以上、やはり基礎基本の知識も深めておくべきだと、とある先生からご指摘をいただきました。
確かに、これまではメンタル面や自分の経験談ばかりをお話ししてきました。
ですが、言語化されている古典的な教えを現代に伝えることも重要だと感じています。
今回ご紹介するのは、剣道で有名な千葉周作先生が作った「打ち込み十徳」という練習方法です。
これは打ち込み稽古をすることで体と心にどのような良い効果があるのかを10個のポイントにまとめたものです。

打ち込み十徳の10項目とは
まずは、千葉周作先生が示した10の項目をご紹介します
- 技烈しくなること
- 打ち強くなること
- 息合い長くすること
- 腕の働き自由になること
- 身体軽く自在になること
- 寸長の太刀自由に使わるること
- 臍下おさまり体崩れざること
- 眼明らかになること
- 打ち間明らかになること
- 手の内軽く冴え出ること
少し難しい古い言葉もありますが、一つずつ現代的に解説していきます。
技術向上に関する効果(1-4項目)
1. 技烈しくなること
これは相手に近づいたらためらわずに連続して技を出していく能力を指します。
昔の武術では、相手を倒すまでしっかりと矢継ぎ早に技を出していく必要がありました。
現代剣道でも、攻めの意識を持って積極的に技を仕掛けていく姿勢は非常に重要です。
切り返し練習を通じて、この激しさを身につけることができます。
2. 打ちが強くなること
これは私がよくお話しする内容ですね。
竹刀で打つときに、しっかりと強さが相手に伝わらなければなりません。
切り返しの中で何回も打つことで、体が鍛えられていきます。
ただ力任せに打つのではなく、正しい打突部位に確実に当てる技術も同時に身につけることが大切です。
3. 息合い長くすること
これは息が長く続くようにすることという意味です。
呼吸法は剣道において非常に重要な要素の一つです。
私の経験では、吐く息を長く、吸う息を短くすると力が入りやすく、気が抜けている瞬間が少なくなります。
実際に打突の機会の中にも、相手が息を吸う瞬間があります。
長く息を吸ってしまうと、そこを打突される可能性があるのです。
切り返しの中で「メン、メン、メン」と息を長く使っていくことで、苦しい状況でも息をコントロールする練習ができます。

4. 腕の働き自由になること
剣道の竹刀は大きく振りかぶってから打つのが基本動作です。
小さい動きだけではなく、強い打ち込みは大きい動作から生まれます。
肩や腕を大きく使って竹刀を振ることで正しい打突が身についていきます。
大は小を兼ねるの考え方で、大きく使うことで小さな動きもできるようになります。
大きく振りかぶれば腰も入りやすく、肩も楽に使えるようになり、自然と胸が張って正しい打突につながっていくのです。

身体能力向上に関する効果(5-7項目)
5. 身体軽く自在になること
これは体が軽くて自由に動けるようになるという内容です。
打つときに体がガチガチになってしまう人がいますが、練習をたくさん積んでいくと、体の無駄な力が抜けて動きがスムーズになります。
興味深い歴史的事実として、武道専門学校(通称:武専)では最初の2年間は打ち込みと切り返しだけを練習して無駄な癖を直していたそうです。
この武道専門学校は、正式名称を「大日本武徳会武道専門学校」といい、現在の武徳殿での八段先生の立ち会いなどにつながる歴史ある組織でした。
6. 寸長の太刀自由に使わるること
昔の江戸時代では長い刀を使う必要がありました。
切り返しの練習をすることで、どんな長さの刀でも自由に使えるようになることが目的とされていました。
昔の刀は現代の竹刀よりもはるかに重く、それだけ腕力と技術が必要だったのです。
7. 臍下おさまり体崩れざること
この「臍下」はよく言われる丹田のことです。おへその下の部分ですね。
体のバランスを良くするために、おへその指3つ分ぐらい下のところに力を入れることでバランスを取ることができます。
実は私の場合、丹田よりもみぞおちに力を入れた方が体がブレにくくなるということを自分で研究し、トレーナーさんにも教えてもらいました。
ただし、丹田呼吸法もあるので、どちらも鍛えていく方が良いと考えています。
体重移動や移動時に体が崩れなくなるのが、この効果の大きなメリットです。
精神・感覚向上に関する効果(8-10項目)
8. 眼明らかになること
剣道では「一眼二足三胆四力」と言われるように、目が非常に重要です。
相手との距離感を身につけるためにも、切り返しで相手との間合いを感じる練習をすることができます。
横から見た方がわかりやすいですが、試合中は正面から見るため、この距離感を身につけることは実戦で大きな効果を発揮します。
9. 打ち間明らかになること
切り返しは本来、元立ちが主体となって行われていた練習だったそうです。
受け手の先生が中心になって行う練習として発展してきました。
相手の動きに合わせて打つ練習をすることで、いつ打ったら良いのか、タイミングを覚える練習をしていたのです。
10. 手の内軽く冴え出ること
これは握る力の使い方を指します。
昔の先生が巻き藁を刀でスパッと切るとき、肩や手に力を入れずに非常にきれいに切っていたそうです。
その秘密は手の内の使い方にあり、切り返しでその技術を覚えることができるとされています。

現代への応用と実践のポイント
これらの「打ち込み十徳」は、単なる体力向上だけではなく、技術・精神・感覚の全てを総合的に鍛えることができる練習方法であることがわかります。
実際に私も長年の剣道経験を通じて、これらの効果を実感してきました。
特に呼吸法や体のバランスについては、現代のスポーツ科学の観点からも検証し、より効果的な方法を模索し続けています。
なお、今回は「打ち込み十徳」についてお話ししましたが、実は「受け八徳」というものも存在します。
こちらについてはまた別の機会に詳しく解説したいと思います。
まとめ:切り返し練習の真の価値
千葉周作先生の「打ち込み十徳」を通じて、切り返し練習の真の価値をお伝えしました。
読者が得られる内容
- 剣道の古典的教えである「打ち込み十徳」の現代的理解
- 切り返し練習で得られる10の具体的効果
- 技術・身体・精神の総合的向上方法
- プロ剣道家の実体験に基づく現代的アプローチ
メリット
✅ 体系的に切り返し練習の効果を理解できる
✅ 古典と現代の知識を融合した学習が可能
✅ 実践的な呼吸法や体の使い方を習得できる
✅ 剣道の歴史的背景も同時に学べる
デメリット
❌ 古典的な表現が理解しにくい場合がある
❌ 現代科学との相違点がある部分も存在
❌ 個人差があるため全ての効果が得られない可能性
剣道の基礎基本を支える古典的な教えを現代に活かし、より効果的な稽古を積んでいきましょう。
正しい情報発信を心がけ、剣道普及に貢献していきたいと思います。
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?