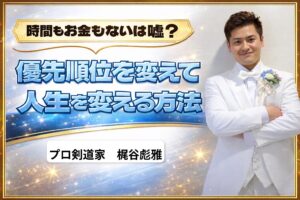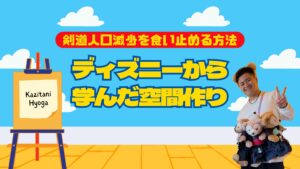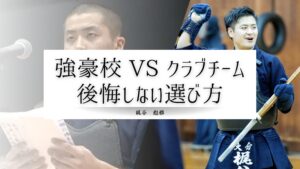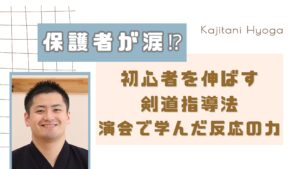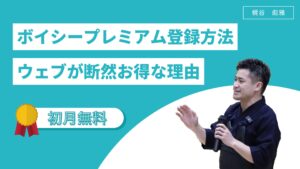時間管理が苦手な私が伝える、時間を生み出す逆説的アプローチ
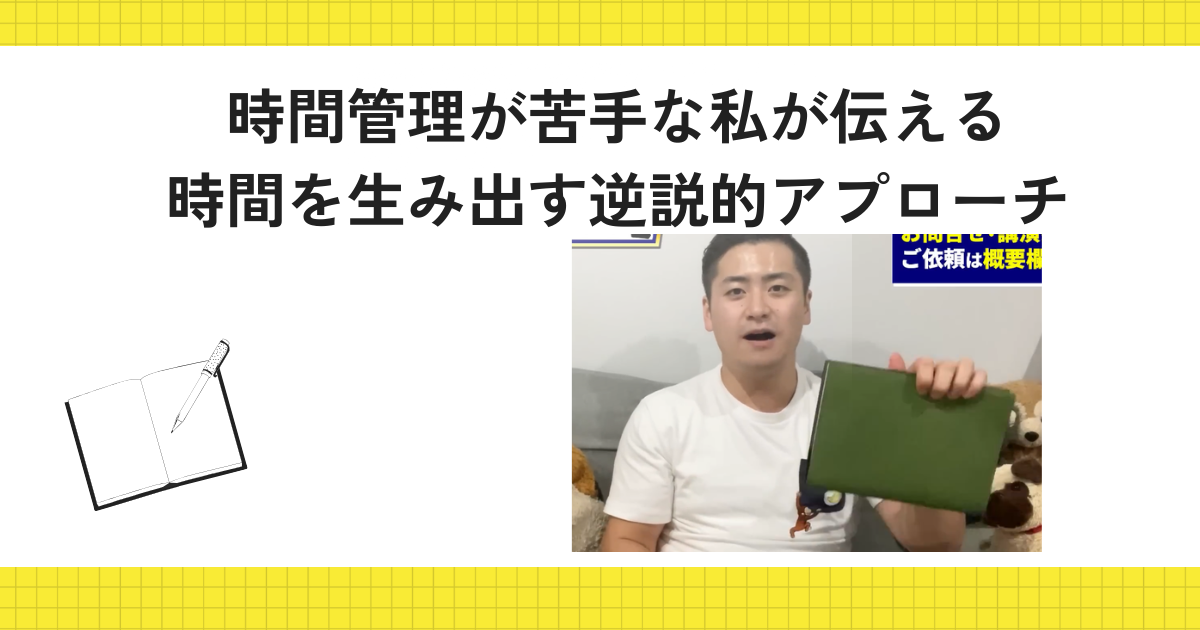


今日のテーマは「時間を生み出すには」というテーマです。
時間管理が苦手な私、梶谷彪雅からお伝えすることで、私と真逆のことをすれば基本的には時間を生み出すことができるのではないかと思い、この記事を作ってみました。
皆さんは、時間があり余って仕方がないという状況でしょうか。
基本的に1日24時間という中で、成果を出せる人と成果を出せない人が出てくると思いますが、皆さんはどちら側にいますか。
そんな悩みを一緒に考えながら、少しでも早く目標達成や成果につなげていただければと思います。
日本一達成の実績から語る説得力
ただ、梶谷彪雅が時間管理が苦手というだけで「何を言っているんだ」という感じになりそうです.
一応私も24時間という中で、中学3年間、高校3年間しかない期間で日本一を剣道で達成したことがあります。
そういった形で、何か成果を出すというところでは参考になるのではないかと思います。
エッセンシャル思考|一つのことに集中して突き進む力
結論からお伝えしますと、これは「エッセンシャル思考」という本を見たことがありますか。聞いたことがある方もいらっしゃるのではないかと思います.
つまり何かというと、物事をいろいろやるのではなく、一つのことに集中して突き進めというイメージです。
マルチタスクの罠|あれもこれもでは成果は出ない
剣道が強くなりたい、日本一になりたい、勉強でも東大に合格したい、仕事でもビジネスとして何かを達成したい。
さらに、親孝行,友達とも仲良くしたいし、先生からも好かれたい,嫌いな人とも仲良く付き合いたい、海外の人にも友達をたくさん作りたい。
英語も勉強してフランス語も勉強して中国語も勉強して韓国語も勉強して、という形でいろいろな目標があることは非常に良いことです。
しかし、あれもこれもしようとすることによって、まんべんなく成長することはできても、何かに特出して成果を収めることは難しいのです。
要は、マルチタスクのような感じになっている人はいらっしゃいませんか。
日本一を達成できた要因|剣道への完全集中
私が中学校時代、高校時代に日本一を達成することができた要因として、やはり剣道に集中できたということがあると思います。
剣道の練習中はもちろん、剣道が終わった後、練習が終わった後もそうですし、次の日の朝もそうです。
寮生活の中でも「もっとこうしたらいいんじゃないか」みたいなことを、とにかく剣道に時間を当てることが多かったと思っています。
土日の休みなどもちろんありませんし、遠征があったり、練習が午前中あったのなら二部練は基本的になかったです。
午後からは剣道の自主練習をしたり、自己トレーニングをしたり、疲れているのであれば整骨院に行ったり、しっかりストレッチをしたり、お風呂に行ったりそういったことをしていました。
選択と集中の重要性|複数の道は日本一を遠ざける
その中でやはり、剣道をしながら日本一になりたいし、プロ野球選手になりたい、プロサッカー選手にもなりたい、サッカーの練習も剣道の練習も野球の練習もとなると、多分わからないんですよ。
日本一、剣道で日本一というのはなれなかったのではないかなと思っています。
これが選択と集中、何か一つにかけるみたいなところかなと思います。

現在の挑戦|プロ剣道家としての選択と集中
私も今は、どちらかというと自分自身がプレイヤー、剣道のプレイヤーとして頑張るというよりは、剣道を普及するために剣道のプロとして剣道だけでご飯を食べていくためにはどんなことをすればいいのか。
あるいは最終的な目標である大会やプロ剣道家、プロチームを作るためにはどんなことを今やるべきなのかというところを一生懸命考えて進んでいるところです。
複数の活動の中での葛藤
ただ、その中でもいろいろやることってありますよね。
YouTubeをしたり、講演会、稽古会をしたり、時にはやはり再生数が回る試合に出場したり挑戦したりしないといけないわけです。
ブログやこのVoicyもそうですし、いろいろ挑戦している私は時間がなくなっていきます。
そうなんです。ここがめちゃめちゃ難しいところです。
「本当にこのVoicyって必要なんだっけ」とか「本当に稽古会が必要なんだっけ、もっとYouTubeにフォーカスして毎日更新するぐらい頑張った方がいいんじゃないの」
とか、もっと挑戦する機会、試合で優勝するために全日本選手権優勝する方が先なんじゃないの、とか。
いろいろ目的達成のため、目標達成の手段に対してのルートってあると思うんです。
山登りに例える目標達成のルート
山登りを例えるとわかりやすいかもしれませんが、山の頂上に登るときに、ゆっくりぐねぐね回っていくルートもあると思いますし、
一直線に上がるルートもあると思いますし、険しい山があるかもしれませんし、楽な登り方もあるかもしれませんよね。そういったイメージだと思います。
どのルートかは初めての山登りなので私はわからないんですよね。ここがすごく大事、いつも言っているところなんですが、環境ですよね。
環境の重要性|成功者から学ぶ最短ルート
例えば山登りのプロがいたりとか、その山に登ったことがある人がいれば、その山頂への登り方、登るスピードというのは間違いなく早くなると思いませんか。
例えばいつも言っていますが、日本一を経験させたことがある人から教えてもらうことで、山登りと一緒のように登り方がわかっちゃうというところですよね。

未開の道を進む難しさ
それで言うと、このプロ剣道家を作った人とかいないんですよ。
大会を作った人っていないんですよね。オリンピック競技を作った人いないんですよね
まだそのあたりという登頂の仕方、山の登り方というのはわからない状態で私は進んでいるわけです。
経験者からのアドバイスの価値
でも、YouTubeをしている人、私よりYouTubeをこれまで経験してきている人というのは、私のYouTube立ち上げ当初から応援してくださっている方がいらっしゃいます。
稽古会を何度も開いたりとか、何度もその目で見てきたり、企画運営したり、クラウドファンディングを立ち上げたり。
居合だったり空手だったり、いろんなことを挑戦しているあやめ先生とかが、私の稽古会を見たりYouTubeを見たりとか、私の活動に対していろんなアドバイスをしてくださっているということはあります。
それによって、間違いなく私一人で山登りをするよりもスピード感というのは確実に登頂スピードは早いと思うんですよね。

成功体験と失敗から学ぶ時間の使い方
私の成功体験と、まだ成功していない時の梶谷と照らし合わせながらお話しさせていただきます。
中学高校の時、日本一を経験させてくれた先生というのは、いろんなことを伝えてくれるわけです。
間違った選択をしてしまう危険性
でも、それだけじゃ私はなんかダメだと思ってやっちゃうんですよね。
例えば高校時代とか入学した当初というのは、「まずやるべきことあるだろう」というのを先生から言われたこともあります。
なんかトレーニングとか、練習が終わった後にやったりしていたんですけど、「もっとやるべきこと、寮の掃除、点呼に間に合うように帰ったり、ご飯食べたり、いろいろやることあるだろう」という優先順位の話ですよね。
あとは時々、怪我をした時とか、怪我をした時にも無理にやったりしていたら逆に怒られてしまいますし、「今は休む時だろう」というように、自分が間違った選択をしちゃうことってたくさんあるんですよ。というか、それが間違いかわからないじゃないですか。
だって、怪我をしていてももしかしたら今踏ん張って頑張った方が成果出るかもしれない、焦りみたいな部分ですよね。
多角的な学びの重要性|友人や専門家からの学び
周りよりスピードをつけるためにどうすればいいかみたいなことって、あまり教えてもらえないんですよ。
だから自分自身でビデオを見て、例えば短距離走の動画を見たりとか、あるいはバスケット選手のトレーニングを研究するとか、いろんなことを自分自身で勉強しながらやっていくわけですよ。
素振りの方法も教えてもらうんですけれども、その中でやっぱりこう、全てつきっきりで教えてくれるわけじゃないので、友達とかに聞いてみるわけですよね。
力を抜く重要性|星子選手からの学び
「星子選手、素振り早くないんだけど、どうすればいいかな。毎日素振りやってんだよって、どうすればいいかな」って思って聞いてみるんですよ。
その時、星子選手から、私は筋肉をつければいいと思ってたんですけど、意外な言葉が返ってきたんですよね。
それが、「素振りはどれだけ力を抜くかが大事だ」と、「力を抜いて振ることが大事だ」と。
私、それ聞いた瞬間に「え?」って思ったんですよ。
素振りってやればやるほど力をつければつけるほどいいんじゃないのって思ったんだけれども
力があったとしても、力の抜き方、力を抜いた瞬間から入れる力というところも勉強しないと早く振れないと。
もちろん振る力も大事だし、打突する力も大事だけれども、それだけじゃダメということが教えてもらって気づくわけですよ。
私は中学校まで知らなかったし、高校で初めて知ったりするわけなんですよね。
専門家からの多角的な学び
こんな形で、先生以外から教えてもらうことというのもあるじゃないですか。
あとは意外と、中学も高校の時も、トレーニングの先生、トレーナーとまではいかないんですけれども、そういった先生とかもいらっしゃったんですよ。
週1回、そういった体幹とか教えてくれる先生がいたりとかあったんですけども、そういったこともやってるわけじゃないですか。
剣道の動きだけじゃないですよね、ということは、それ以外から剣道に転用できるみたいな部分もあると思うんですよね。

一つに特化すべきか、多角的に取り組むべきか
ということは、多分私のこの人生経験上、何か一つに特筆する、素振りだけを極めるとか、面打ちだけを極めるとか
小手打ちだけを極めるという方法で日本一というたどり着く方法もあるんだけれども、それだけではないと。
実績の必要性
誰かを強くしないと、そういった実績がないと、日本一に誰かをさせること、それがプライベートレッスンなのか、どこかの高校で教えることなのか、そういった実績が必要かもしれないですし
自分がある程度勝つ姿とか挑戦する姿というのを見せないといけないかもしれないですし、このVoicyみたいに情報発信しないといけないかもしれないですし、それがわからないんですよね。
バランスの難しさ|エッセンシャル思考との葛藤
でも、それをやればやるほど、先ほどの一番最初の話に戻りますが、エッセンシャル思考みたいな部分にならなくて、結局あれもこれもになってしまって、日本一から遠ざかってしまう
どれも中途半端になってしまうということにもなりかねないなという、ここのバランスが非常に難しいなと思っています。
時間は有限|ただやればいいわけではない
特に時間というのは、毎日24時間って限られた中で、やっぱり単にやればいいというだけじゃないと思うんです。
努力の方向性|星子選手との違い
これは高校時代にあった話なんですけど、私がめちゃめちゃ努力する、実際に走ったりとか素振りをしたりとか筋トレをしたりとか、そういったことをするという方法もあると思うんです
星子選手とかそれを見て、「それだけ俺は頑張れないと。
やりすぎると俺怪我しちゃって、逆にその目標達成することができなくなっちゃうから」っていう感じで、人によっても違うと思うんですよ。
最も大事なこと|目標を明確にする
なので、ただ一番大事なことは目標を明確にするということですよね。
星子選手も私も、その他中学校の友達も、みんな日本一になるという目的に向かって頑張っているじゃないですか。
団体戦に例える役割の明確化
これを団体戦に例えると、日本一を達成するための先鋒の役割、次鋒の役割、中堅の役割、副将の役割、大将の役割っていろいろとあるんです。
これを思っていると思った時に、「今、私が頑張るポジションって何なんだろう」という感じのことがありますよね。
中学であれば、大将として大将戦に回れば絶対に勝たないといけない場面では勝たないといけないです
代表戦になれば勝たないといけないですし、高校であれば副将というポジションだったので、なんとか大将に繋げないといけないというポジションだったと思います。
現在の役割|情報発信と挑戦
今だったら、まず剣道の稽古法を発信することで剣道を楽しんでもらうとか、強くなるための情報を発信することで信用してもらうとか
挑戦する姿を見てもらって「自分も挑戦したいな」と思う人を増やしたりとか、例えばこれからやっていく剣道を普及するために道場を作る。
これ、初めてで、このゼロから1、剣道をやってない人を剣道を始めさせる、始めていただくというところに繋がると思っています
今後その挑戦するというところにつながると思っていますし、挑戦するということが新たに稽古会を開いてみたいなって思う人が実際に、今度そういった人がいてくださって、稽古会を開きたいですっていう方がいらっしゃったりするんです
そういった人がどんどん増えると、日本全国的にも剣道を盛り上げる、盛り上げたいっていう人が増えていくかもしれない。
これも剣道普及だと思いますし、同じく道場を立ち上げて剣道をする人を一人でも増やしていきたいって思う人も増えるかもしれないですね。
道場を立ち上げることによって、いろいろ剣道復旧のやり方ってあると思うんです。

やらないことを見極める|成果に結びつく行動の選択
ここまで来て、あと重要になるポイントというのはやらないことを見極める、これに尽きるかなと思います。
成果に結びつく行動の具体例
例えば、素振りをめちゃめちゃ一生懸命頑張って成果が出る、振りの速さがつくとか打突力がつくとか、この成果に結びつけたらいいと思いませんか。
下半身、スクワットをする、50m走を10本走るという、して下半身のスピードが速くなる、そうすれば日本一に近づけると思いませんか。
戦い抜く体力をつけるために毎朝5km走る、それによって成果が結びつければ、実際に個人戦の延長で疲れにくくなったという成果がつけば、それは日本一達成に向けて近づいていると思いませんか
という形で、何か成果に結びつけていればいいんじゃないかなと思います。
成果測定の重要性|SNSや活動の見直し
できている時とできていない時の比較をした時ですね。
例えばSNSを見る時間というのが、本当に目標達成するための成果に近づいているのかなというところは、ものすごく大事になってくるポイントかなと思います。
私ができていなかったこと|ブログとVoicyの反省
じゃあ何が私できてなかったかというと、例えばブログとか運営してたりとか、Voicyとかもやってるんですけれども、1年間やり続けて、そこまでフォロワーが劇的に増えたわけでもないですし、視聴者維持率というのが増えたわけでもない。
その中で、ブログの書き出しはしているんですけれども、その書き方の外注費ってかかってくるんですよ。
外注費かかっている割に、実際に講演会増えたのかなとか、本が売れてるのかなとか、クリックされてるのかな、見られてるのかなという成果、効果測定というのができてなかったんですよね。
これ、せっかくやってるのに成長できてるかわからないって、全然意味がわからないですね。
一生懸命毎日1万本素振りしてたのに、素振りの速さ全く変わってないってなったら、もう何のためにこの時間使ってきたんだってなるじゃないですか。
この成果というのは改めて大事なところだなというところに最近気づかされました。
実践のためのアドバイス|振り返りとリスト化
なので、皆さんもぜひ、何か目標を立てて行動していくときは、24時間という限られた時間なので、少しでも成長できてるのかなというところをぜひ見ていただきく。
その振り返り方というのは、私のいつも言っていますけど、メンバーシップとかに入っていただくと振り返りやすかったりすると思います。
まとめ|限られた時間で最大の成果を出すために
この記事では、日本一を達成した剣道家の実体験をもとに、時間を生み出すための本質的な考え方を解説しました。
重要なポイント:
- エッセンシャル思考:一つのことに集中して突き進むことで、特出した成果を出すことができる
- 環境の重要性:成功者から学ぶことで、目標達成への最短ルートを見つけられる
- 目標の明確化:自分の役割とポジションを理解し、何に集中すべきかを明確にする
- やらないことを見極める:成果に結びつかない行動を排除し、効果測定を行う
メリット
- 限られた時間で最大の成果を出せる:選択と集中により、特定の分野で日本一レベルの結果を達成できる
- 迷いが減り行動が明確になる:やるべきことが明確になることで、無駄な悩みや迷いの時間が削減される
- 成功への最短ルートが見つかる:経験者や専門家からのアドバイスにより、遠回りせずに目標達成できる
- 成果測定により改善サイクルが回る:行動の効果を可視化することで、常に最適な方法を選択できる
- 多角的な学びで応用力がつく:一つの分野に集中しながらも、他分野からの学びを転用できる
デメリット
- 選択を間違えるリスクがある:一つに集中するため、方向性を誤ると大きな時間のロスになる可能性がある
- 他の可能性を捨てる覚悟が必要:マルチタスクを諦めることで、他の分野での成長機会を失う
- バランスの見極めが難しい:完全に一つだけに絞るべきか、関連する複数のことに取り組むべきか判断が困難
- 成果が出るまで時間がかかる場合がある:特に未開の道(プロ剣道家など)では、正解がわからず試行錯誤が必要
- 周囲の理解が得られにくいことも:一つのことに極端に集中すると、周りから「もっと他のこともやるべき」と言われる可能性がある
本日も最後までご清聴いただき、本当にありがとうございました。今日も皆さんにとって最高の一日になりますように。
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?