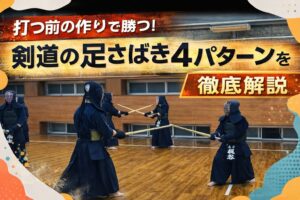剣道の基礎基本とは?プロ剣道家が語る本当の意味と実践的指導法



学べること
- 真の基礎基本の定義と一般的な誤解
- 段階別指導法における適切なタイミング
- 実戦的基礎基本の身につけ方
- 目的に応じた練習の重要性
読者対象
- 基礎基本を見直したい中級者以上の剣士
- 指導方法に悩む剣道指導者・先生
- 子どもの剣道指導に関わる保護者
- 強くなるための練習法を模索している剣道愛好家
プロ剣道家が考える「基礎基本」の本当の意味
今日は「基礎基本とは」というテーマで、皆さんが頭の中で思い描いている基礎基本と私の考える基礎基本の違いについてお話しします。
一般的な基礎基本の定義
一般的に基礎基本とは、どんなスポーツ、勉強、仕事でも一番最初に身につけるべき土台となる力、動作、知識のことを指します。
簡単に言うと、すべてのスタート地点となるものです。
具体例を挙げると
- 剣道:構え方、竹刀の握り方、足さばき
- 野球:キャッチボール、素振り、腕の振り方
- 算数:足し算、引き算
- ビジネス:挨拶、連絡、相談、報連相
これらがしっかり身についていないと、どんなに難しい技術や作戦を学んでも、途中でつまずいてしまう可能性があります。
だからこそ、まずは基礎基本を大事にしましょうという考え方が一般的です。
実体験から学んだ基礎基本指導の重要性
4歳の娘への指導体験
私自身、剣道を習い始めた時に最初に教えてもらったのは足さばきでした。
すり足で前に行く、後ろに行く、右に行く、左に行く、右斜め前、左斜め後ろといった足さばきの練習です。
同時に「剣は心なり」という言葉も覚えて、足さばきをしながら竹刀を持って素振りをするという流れで、少しずつ剣道の基本動作を学んでいきました。
現在、4歳の娘がいるのですが、面打ちを打った後に「すり足で抜けなさい」と言っても、「すり足って何?」という感じになってしまいます。
まだ馬のような感じで抜けているだけで、基本動作が全然身についていない状態です。
この経験から、基本動作を教えておかないと剣道の形にならず、ただのあてっこになってしまうということがよくわかります。
基礎基本指導の段階別アプローチ
初級段階:最低限の基本動作習得
ある程度基本動作が身についてきた段階、つまり
- すり足ができる
- 素振りができるようになってきた
- 踏み込みができるようになってきた
- ベースとなる素振り、打ち込み、切り返しができる
この段階で何をさせるかが重要なポイントです。
中級段階:応用技への移行タイミング
基礎ができた段階で、小さい面打ち、面フェイント面打ち、面フェイント小手打ちなど、より高度な技術に移行します。
しかし、これらの二段技は
- ある程度まっすぐな面打ちができないと難しい
- 2回踏み込まないといけない
- 小手を打った後の体当たりの仕方
- 右にさばく技術
など、基礎基本よりもはるかに複雑になってきます。

「質」と「量」のバランス – 彪進会での実践指導
量の重要性と前提条件
彪進会に参加してくださる方々は、ある程度試合もできるようになって強くなりたいという段階の選手たちです。
そこで私は「量の方が大事」と伝えていますが、これには重要な前提があります。
4歳の娘の例でいうと、腕もグニョングニョンの状態で素振りをして、手首だけの素振りになっている状態で100本やっても、あまり効果が期待できません。
つまり、量が大切というのも、最低限の基本動作ができていることが前提条件なのです。
段階に応じた指導方針の変化
彪進会では県上位チームの選手も参加していますが、ある程度基礎基本ができている選手でも、強く打とうとしたり速く振ろうとすると
- フォームが崩れる
- 肩に力が入る
この時、私はあえて「フォームがちょっと崩れてもいい、全力で振れ」と指導します。
型を破る勇気 – 成長のための意識的な基礎基本逸脱
プロ指導者の判断基準
基礎基本をある程度マスターした選手に対して、私は以下のように指導します
「音が出るように全力で振れ」
「強く打てるように全力で強く打て」
「体がグニャグニャになってもいい、それでも強く打つ意識をしろ」
これは一見、今まで教えてきた基礎基本を度外視した指導のように見えます。
実際に批判される部分もあるでしょう。
目的に応じた練習の重要性
しかし、最終的に大事なのは今何を目的にして練習をしているのかです。
基礎基本動作(すり足、素振り、右足前、左足引きつけながら打突、右足踏み込みながら打突)ができたら
- 強く打つ
- 速く素振りをする
- 速く移動する
- 最初はブレてもいい、型から破れてもいい
- できるようになったら(パワーがついたら)もう1回基礎基本に戻す
- パワーが足りない部分に気づく
- また型を破る
この繰り返しプロセスこそが、真の成長につながるのです。
実戦で通用する基礎基本の身につけ方
段階的レベルアップ戦略
私が考える基礎基本指導の流れは以下の通りです
| 段階 | 重点項目 | 指導方針 |
|---|---|---|
| 初級 | 正確な動作 | 型を重視、丁寧に |
| 中級 | パワー・スピード | 型が崩れても全力で |
| 上級 | 精度とパワーの融合 | 基礎基本に戻しつつパワーアップ |
この循環を繰り返すことで、単なる型だけの基礎基本ではなく、実戦で通用する真の基礎基本を身につけることができます。
指導者が持つべき視点
指導者として大切なのは
- 選手の現在のレベルを正確に把握する
- 目的に応じた練習方法を選択する
- 型を破る勇気を持つ
- 基礎基本への回帰を適切なタイミングで行う
これらの要素を組み合わせることで、選手はより高い次元での成長を遂げることができるのです。
まとめ
基礎基本は決して固定的なものではありません。
選手の成長段階と目的に応じて、柔軟にアプローチを変えていくことが重要です。
この記事で得られる内容
プロ剣道家の実践的指導理論を通じて、従来の基礎基本指導の概念を覆し、より実戦的で効果的な練習方法を学ぶことができます。
4歳の娘への指導体験から彪進会での県上位チーム指導まで、幅広い実例を基にした具体的な指導法を習得できます。
メリット
- 段階別指導法により効率的な成長が可能
- 目的に応じた練習で無駄のない練習時間を実現
- 型を破る勇気で従来の限界を突破
- 実戦的基礎基本で試合に直結する技術向上
デメリット
- 従来の指導法との価値観の違いで混乱する可能性
- 適切なタイミング判断が難しい
- 型を破る段階で一時的な技術低下が起こる場合がある
基礎基本を固定概念として捉えるのではなく、成長のための手段として活用することで、あなたの剣道はさらなる高みへと導かれるでしょう。
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?