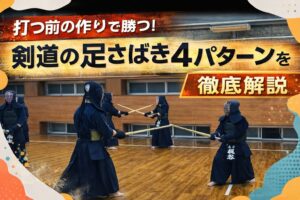【完全版】剣道の踏み込み練習法『音』は重心移動で決まる
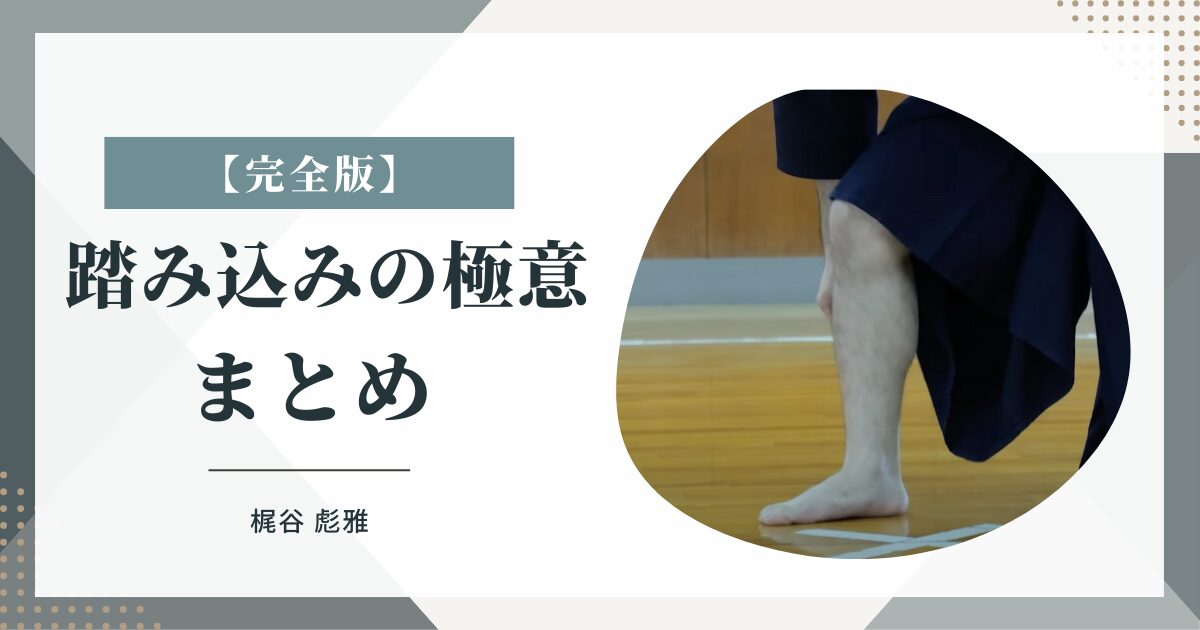
「踏み込みの強さは、打突力よりも怖い」
これは、数々の強豪選手と対戦してきた中で感じる実感です。
打突が強いだけなら、触られても「まあ大丈夫かな」と思えますが、踏み込みが強い選手は違います。
「パカン」と響く音に威圧され、打った後のキレ(残心の美しさ)によって一本になりやすい。
それが、踏み込みの真の威力なのです。
本記事では、剣道における踏み込みの重要性から具体的な強化方法、正しいフォーム、よくある悩みの解決法まで、実戦で使える踏み込み技術を完全解説します。

踏み込みについての動画はこちら
踏み込みの重要性 – なぜ強い踏み込みが必要なのか
踏み込みとは
剣道における踏み込みとは、打突の瞬間に右足で床を力強く踏み込み、体重移動と共に技の威力を最大化する動作です。
「一眼二足三胆四力」の格言が示すとおり、剣道では足さばきが極めて重要で、その中でも踏み込みは気剣体一致を実現する要となります。
なぜ踏み込みが一本につながるのか
- 音の威力 – 強い踏み込み音は相手に心理的プレッシャーを与える
- 打突力の向上 – 体重移動により打ちの威力が格段に上がる
- 残心の美しさ – 踏み込み後のキレが良くなり、審判の印象が向上
- 次への準備 – 正しい踏み込みは次の動作への移行をスムーズにする

2. 踏み込みの基礎知識
正しい踏み込みの手順
基本的な流れ
- 構えからの準備 – 左足のかかとを軽く浮かせ、重心を前に
- 右足の踏み出し – 膝を前に出すイメージで足を送る
- 着地 – 足裏の真ん中(かかとより)で踏み込む
- 左足の引きつけ – 自然に左足を引きつけて体勢を整える
タイミングのポイント
- 打突動作と同時 – 竹刀が振られる瞬間に踏み込む
- 重心移動 – 上から下に落ちる力を利用する
- 膝の位置 – 膝の下で踏み込むことで蹴り足にならない
理想的な音の特徴
- 「ドン」と「パン」の中間音 – かかとだけでもつま先だけでもない
- 短く鋭い音 – 長く響く音は接地時間が長すぎるサイン
よくある間違い
- 強く踏み込もうとするのはNG
- かかと着地 – 「ドスン」という重い音になる
- つま先着地 – 「ペチペチ」という軽い音で威力不足
- 手足がバラバラ – タイミングがずれて効果半減
- 膝より前の着地 – 蹴り足になり前への推進力が弱くなる
一番難しいのが『重心移動』です。
そしてよくある間違いとして、強く踏み込もうとすることが挙げられます。

強い踏み込み:重心移動
強く踏み込む意識も重要ですが、間違った踏み込みで強く踏み込むと「怪我」につながります。
そのため、一番最初に練習するべきなのが重心移動です。しかし、習得が一番難しいのも重心移動です。
重心移動のイメージは踏み込むより、体重が自然と乗る感覚です。
ジャンプをすると重力により自然と着地すると思います。着地する時は自分の体重が両足に乗ると思います。
自然に体重が乗る瞬間に踏み込む感覚を加える
面打ちや小手打ちの動作でも同じように、左足で地面を蹴って着地する瞬間だけ力を入れるようにする事が大切です。
空中で無理に力を入れたり、力を入れるのが遅くなるといい音が鳴らないので注意しましょう。

3. 踏み込み強化の3つの柱
第1の柱:かかとの強化
踏み込みで最も重要なのは、痛みを恐れずに強く踏み込める足を作ることです。
踏み込んだ瞬間に痛いと、思い切り踏み込めないと思うので、参考にしてみてください。
ビール瓶を使った強化法
空手の鍛錬法からヒントを得た方法です。
実は空手の選手は脛(すね)で相手を蹴るので、脛の強化をしています。
その方法を踵の強化にも応用します。
やり方:
- ビール瓶などの硬い瓶を用意
- かかとを瓶で軽く叩く(最初は優しく)
- 徐々に強度を上げて100回、200回、300回と増やす
- テレビを見ながらでも継続可能
効果:
- かかとの耐性向上
- 踏み込み時の痛み軽減
- より強い踏み込みが可能に
小手打ちも最初は痛いですが、長く剣道をしていると小手打ちの打突にも慣れてきます。
逆に長期間剣道をしていないとまた痛くなります。なので、踵の強化も最初に継続的に行うことで長期的に剣道する人のサポートにつながります。
足つぼマッサージ公園の活用
硬い石の上を歩くことで足裏全体を強化します。
段階的アプローチ:
- 第1段階 – 石の上をゆっくり歩く
- 第2段階 – 石の上で軽い踏み込み練習
- 第3段階 – 石の上での本格的な踏み込み
安全上の注意:
- ガラスの破片などがないか十分確認
- 怪我のリスクを考慮し、段階的に強度を上げる
- 足裏に傷がある時は避ける

裸足でのランニング・踏み込み練習
アスファルトなどの硬い地面での練習も効果的です。
これは実際に中学や高校時代にやっていました。
道場ではなく、体育館で練習していたので、コンクリートの上で踏み込みをして、ビール瓶同様に慣れさせて行く感じです。
実践方法:
- アスファルト上での踏み込み練習
- 足裏全体の感覚を養う
重要な注意点:
- 安全第一 – ガラスや危険物のチェック必須
- 段階的に – いきなり長時間は禁物
- 道場での正しいフォームありき – 硬い地面だけでは間違った踏み込みになる可能性

第2の柱:正しい踏み込み方法
足の着地位置の最適化
- かかとだけNG – 「ドンドン」という重い音
- つま先だけNG – 「ペチペチ」という軽い音
- 理想の位置 – 足裏の真ん中(かかと寄り)で「パン」という音
先ほどもお伝えしたように、音のイメージは「ドン」と「パン」の間です。
文章だと伝わりにくいと思うので、動画を確認してみてください!下記の動画は踏み込みの瞬間から流れるようにしています。
参考動画で確認!
膝の使い方
- 膝の下で踏み込む – 蹴り足にならない最重要ポイント
- 膝を前に出すイメージ – 足を出すのではなく膝から
- 膝より前の着地を避ける – 推進力が落ちる原因
打突の時につま先から出て、戻り足になる人が居ます。これは非常に勿体無いです。
無駄な動作に繋がってしまうので、膝から出る感覚を習得する事が重要なポイントです。
第3の柱:重心移動の習得
重心移動の感覚を掴む方法
ジャンプ練習法:
- 軽くジャンプ – 高く跳ぶ必要なし
- 着地と同時に踏み込み – 自然な重心移動を利用
- 上から下の力を前方向へ – 真下に落ちるのではなく前進
これも文章だけだとわかりにくいと思うので、先ほどの動画の重心部分を確認すると少しイメージが湧くと思います
重心の部分の動画を確認
重心移動のメカニズム:
- 飛んでいる状態は重心が上方向に
- 浮いた重心は重力に従って落ちてくる
- 重心が落ちる力を活用して強い踏み込みを実現
- 打突動作とのタイミングを合わせる
重心移動の考え方は分かったとしても、重心移動と踏み込みを合わせるのは難しいです。
これは「量」をこなして身につけていきましょう。
4. レベル別練習メニュー
初心者向け(毎日5-10分)
基礎練習
- その場踏み込み –
正しいフォーム習得(20回×2セット) - 素振りとの組み合わせ
面打ち素振り+踏み込み(15回×2セット) - 音の確認 – 「ドン」「パン」「ペチ」の違いを意識
フォームチェックポイント
- 膝の下で着地できているか
- かかととつま先の中間で踏めているか
- 手足のタイミングは合っているか
中級者向け(週3-4回、15分)
面をつけずに初級編を練習してできるようになったら、技の練習の中で活用しましょう!
実践的練習
- 面打ち練習 – 相手との距離感を意識した踏み込み
- 連続打ち – 面→面、小手→面での踏み込み練習
- 応用技 – 出鼻技、引き技での踏み込み応用
上達のポイント
- 様々な間合いでの踏み込み
- 疲労時でも正しいフォーム維持
- 相手の動きに合わせた踏み込みタイミング
ここで重要なのが、面をつけて技の練習をしたとしても『重心移動を意識できるか』がポイントです。
面をつけた瞬間に意識が技の方に向きがちなので、踏み込みを意識して練習をしましょう。
意識ができない場合はもう一度、初級編に戻って練習してみましょう。

上級者向け(週3回、20分)
実戦練習
- 二段打ち – 面→小手面、面→胴での連続踏み込み
- 応じ技 – 相手の攻撃に対する反応での踏み込み
- 試合形式 – 実際の試合を想定した総合練習
極意
- 疲労困憊時でも美しい踏み込み
- 相手の心理を読んだタイミング
- 最小限の力で最大効果の踏み込み
上級編では、二段打ち、三段撃ちになったとしても踏み込みが完璧にできる状態を目指します。
さらに技の練習ではなく、試合の中で無意識レベルで重心移動からの踏み込みができたら完璧です。
ここまでくるのに私は高校生でも半年以上かかりました。
中学校までは『ドン』という音の踏み込みだったので、修正にかなり苦労しましたが、おかげさまで一生物の踏み込みを習得できました。
5. よくある踏み込みの悩み
Q1: 踏み込みで足が痛くなる
原因: かかと着地、硬すぎる体育館での練習
解決策:
- 足裏の真ん中での着地を意識
- 段階的な強化トレーニング
- 踵サポーターをつける
私は踵サポーターをあまりおすすめしていません。理由は踵サポーターに慣れてしまうからです。
なので今回紹介した、踵を強化する方法が理想です。しかし、稽古をしないといけない人もいると思います。
練習では踵サポーターをつけて練習をして、自主練習で踵の強化や正しい踏み込み練習をしながら、踵サポーターを外せる努力をしましょう。
Q2: 音が出ない・小さい
原因: 着地位置の問題、体重移動不足
解決策:
- かかととつま先の中間位置を確認
- 重心移動の練習(ジャンプ法)
- 道場の床の状態も確認
Q3: 手足がバラバラになる
原因: タイミングの同調不足
解決策:
- ゆっくりとした動作で同調性を確認
- 「足→腰→手」の順番を意識
- 打ち込み台を使って確認
- 意識的に手と足を合わせる練習
手と足が合わないことで悩まれる選手も多いと思います。
その多くの選手が無意識に打突をしていることが多いです。
なので、意識的に練習をする。意識練習が完璧になるまで無意識練習はしないほうがいいです。
無意識で手と足が合わない状態が続くと、それが癖になって、修正するのにものすごく時間がかかります。
まずはゆっくりでもいいので意識練習に取り組みましょう。

Q4: 踏み込んだ後のキレが悪い
原因: 左足の引きつけ不足、重心が残る
解決策:
- 左足の素早い引きつけ練習
- 右足の筋力強化(重要)
- 前方向への体重移動を意識(左足強化)
踏み込みの重心移動ができたとして、その後のキレが悪い場合は『右足の筋力』を高めるのが一番効果的です。
そして、左足の引き付けを意識した練習によって『腸腰筋』を鍛える。
この2つをすることで、打突後のキレは改善されます。
それでも遅い場合は、左足の脚力不足で前に行く推進力が足りない可能性があります。
まずは前に体を押し出すための左足強化をしましょう!
Q5: 相手との距離によって踏み込みが変わってしまう
原因: 間合い感覚の不足、踏み込み幅の調整不足
解決策:
- 様々な間合いでの練習
- 膝の位置は一定に保つ
- 足捌きとの組み合わせ練習
相手によって変化させるのも上級者練習です。
面をつけての技の練習が完璧にできるようになったら、次のステップとして『元立ちに動いてもらう』という技の練習をします。
ただ、打たせるのではなく、前に出てくるパータン練習や、下がるタイプのパターン練習をしていきます。
どちらのパターンでもできるようになってきたら、打突の瞬間に、前か後ろかその場、どれかを相手に選択してもらうようにしましょう。
そうすることでより実践的な技の練習をすることができます。
6. 成長へのアドバイス・モチベーション維持
継続のコツ
1. 小さな変化を記録する
- 音の変化を録画・録音して客観視
- 練習日誌で感覚の変化を記録
- 定期的な自己チェック
2. 段階的な目標設定
- 1週目: 正しいフォームの習得
- 1ヶ月目: 安定した踏み込み音
- 3ヶ月目: 実戦での効果的な踏み込み
3. 指導者・先輩からのフィードバック活用
- 定期的な指導を受ける
- ビデオ分析による改善点発見
- 他の剣士との比較学習
踏み込みの音や練習方法があっているかどうかを確認するために『試合分析・稽古分析』を梶谷彪雅に依頼してみましょう!
踏み込みマスター後の発展
次のステップ
- 有効打突の習得 – 踏み込みを活かした確実な一本
- 送り足の向上 – 踏み込みからの継続技術
- 間合い管理 – 踏み込み距離の最適化
- 心理戦術 – 音による相手への威圧
踏み込みが完璧にできるようになると、すべての技が1本になりやすいです。
逆に踏み込みが無い状態での技の練習時間は勿体無いと言っても過言ではありません。
まずは踏み込みの力で1本にできるレベルまで練習しましょう。
7. よくある質問(FAQ)
Q: 硬い体育館と道場の違いはどう対応すべき?
A: 常に固い体育館の場合は、踵の強化と正しい踏み込みの習得を優先するべきだと思います。
どうしても難しい場合は踵サポーターを使いましょう。
遠征などで硬い体育館の場合は、適宜サポーターを使うのがいいかと思います。
いつも柔らかい場所からの環境変化に対応するのは上級者向けです。急な環境変化にも対応できるように強化は必要です。
Q: 足の強化練習は必ずやるべき?
A: 絶対ではありませんが、踏み込みの痛みを恐れて弱い打突になるくらいなら、安全に配慮した範囲で強化することをおすすめします。
ただし、怪我のリスクを十分理解した上で行ってください。特にアスファルトの上でやる練習などは注意です。
まずはビール瓶で力をコントロールできる状態がおすすめです。
Q: 女性や体重の軽い人でも強い踏み込みはできる?
A: 可能です。正しいフォームと重心移動により、体重に関係なく効果的な踏み込みができます。
Q: 踏み込み練習で注意すべき怪我は?
A: 主にシンスプリント(すねの痛み)、足底筋膜炎、かかとの打撲などです。
ふくらはぎと脛の筋肉はしっかりマッサージし、段階的に強度を上げることが重要です。
8. まとめ – 強い踏み込みで一本への道筋
踏み込みの強化には以下の3つの要素が欠かせません:
重要ポイントの再確認
- かかとの強化 – 痛みを恐れない足作り
- 正しい踏み込み方 – 膝の下、足裏の適切な位置
- 重心移動の習得 – 上から下の力を前方向へ
実践での活用
- 音の質 を重視(大きさより短い収束音)
- タイミング の同調(気剣体一致)
- 継続性 で次の動作への準備
安全への配慮
- 段階的な強化トレーニング
- 適切な休息とケア
- 指導者の下での練習
踏み込みは一朝一夕では身につきません。
しかし、正しい方法で継続的に練習することで、必ず「パカン」と響く美しい踏み込み音と、一本につながる威力ある打突を身につけることができます。
今日から始めて、半年後の自分の踏み込みの変化を楽しみにしながら、日々の稽古に励んでください。
強い踏み込みは、あなたの剣道を必ず次のレベルへ押し上げてくれるはずです。
関連記事
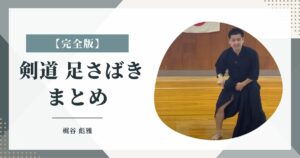

本記事は梶谷彪雅の指導内容を基に、剣道の踏み込み技術について詳しく解説しています。練習の際は安全に十分注意し、指導者の下で行うことをおすすめします。
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?