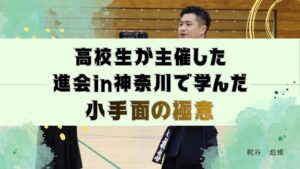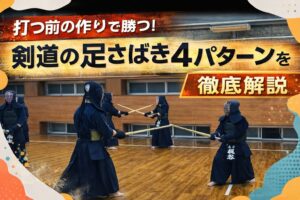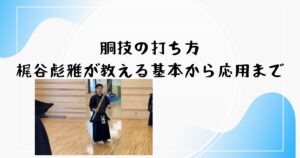引き胴で試合を制する|梶谷彪雅が教える胴打ちの極意



今日は引き胴(ひきどう)という難しくも最高に効果的な技についてお話しします。
昨日の放送をまだ聞いていない方、返し胴や飛び込み胴についても知りたい方は、ぜひ前回の記事をご確認ください。
引き技が難しい理由|3つの要素が全て揃う必要がある
まず下がるという動作自体がめちゃめちゃ難しいんですよね。
特に大人で始めた方や、剣道から何十年も離れていたという方が引き技を教わると、本当に大変だと感じると思うんです。
引き技を決めるには、3つのポイントが全て揃わないといけません。
引技については動画で詳しく解説しています
引き技が決まる3つの条件
- 打突力の強さ……弱いと打ったように見えない
- 踏み込み力の強さ……弱いと一本になりづらい
- 下がるスピードの速さ……遅いと間合いが切れない
どれか一つでもかけていると、なかなか決まりづらいんですよ。
打突力が強くても踏み込みが小さいと一本になりづらいですし、踏み込みが強くても下がるスピードが遅ければ、やはり一本になりません。
どれも極めないと、なかなか一本になりづらい難しい技だなと思います。
強い打突の極意は重心を剣先に乗せるが重要
現役生こそ引き技を極めるべき理由
ただ特に現役生の方は、この引き技を制することができれば、逆に試合を有利に働かせることができます。
大事な場面でここぞという時に、一本にすることができるんです。
これはめちゃめちゃメリットのあることなので、絶対に勝負どころで勝ちたいという人は、引き技を極めた方がいいんじゃないかなと思います。
強豪校も、結構煮詰まってくる時ってあるじゃないですか。
やばい、絶対に勝たないといけないみたいなところで、延長続きの場面とかで煮詰まってきた時に、思い切った技で勝負するってリスク高くて怖いんですよね。
でも、自信があれば話は別です。
自信があれば、それはリスク高いではなくて、自信の技になっているので一本になる可能性があるんです。
一方、いやここでいったら打たれるかもって思った中途半端な技というのは、どうしても一本になりにくかったりします。
その気持ちが審判に見えたり、相手に見えたりするんですよね。
だったらリスクが低くて、相手が気を抜いているところを打てるんだったら、そっちの方が良くないですか。
リスクが低いんで、ここだったらいけるって思い切った技につなげられるんですよね。
それが引き技のめちゃめちゃいいところなので、ぜひ極めていただきたいなと思います。
引き胴の基本|まずは引き面を習得しよう
引き胴を打つために、一番大事なことから説明します。引き胴を打ちたかったら、まず引き面を狙ってください。
なぜか。引き面を打つことによって手元が上がるからです。そして相手が面を避けるからです。
危ないなって面を避けるからこそ、引き胴が狙いやすくなるんです。ここが重要なポイントですね。
引き胴を打つための大前提:
一本になりそうな引き面を打つことで、相手の手元が上がり、胴が空きやすくなる。
引き面を効果的に狙うコツ|つばずれ際のタイミング
では、引き面をどこで狙うか。
つばせり合いの状態でお互い気を張っている状態から狙うというのは、かなり難しいんですよ。
もちろん狙うことできるんですが、難易度が高いですね。
ここからが少しずるい考え方なんですが、これやっぱり強豪校とかでやっていることなんです。
今の剣道ルールだと、つばずれになって3秒間ぐらいで別れましょうねというルールですよね。
その時になんとなく別れる人が多いじゃないですか。
そろそろ3秒かなとか考えて別れてる人、少ないんじゃないかな。
つばぜり合いになって、なんとなくお互い別れましょうという感じになりますよね。
相手を油断させるテクニック
この時に、ちょっと早めのタイミングで別れるんですよ。
つばぜり合いになってなんとなく別れる。
もちろん相手の引き面は警戒しつつで、なんとなくが定着してきた時に、相手はなんとなく下がっているんです。
そこを狙うということですね。
延長続きになってくると、なんとなく別れちゃうじゃないですか。
そういった時に別れようとする瞬間、3秒以内あるいは3秒から4秒に差し掛かるぐらいのところでも技を出して、反則をもらうってことってあんまりないと僕は思ってるんですよ。
もちろん反則を取られた状態でやってしまって反則になると怖いんで、発動条件としては反則になる前というところだとは思います。
3秒以内だったら別に打っていいというルールなので、なんとなく別れるタイミングを早めるというのが今回のポイントです。
なんとなく別れさせておいて、3秒以内の別れようとするところを狙うというところをやってみてください。
相手が下がろうとする瞬間を狙う
この時に大事なのが、相手が下がろうとする瞬間だということです。
だから、自分も下がりながら打つと当たらないんですよ。
そうではなく、ちょっと前に出ながら、半歩前に出ながら引き面を狙うというのがポイントです。
引き面はここまでにしておきますが、別れ際をしっかり狙ってみると、相手は引き面があるって頭の中にすり込まれていくと思います。
すり込まれた状態で引き胴を狙っていくということですね。
引き胴の打ち方|フェイントから実践まで
引き胴の打ち方なんですが、ただ引き胴を狙ってもやっぱり手元が浮きにくいですよね。
相手に「あ、これ胴か」って気づかれてしまいます。
いかに最初の引き面に見えるような形で引き胴を打つか、ここがものすごく大事になってきます。
パターン①:面のフェイント→引き胴
例えば面のフェイントするために、面を触ってから引き胴を打ったりとか。
あるいは、押して自分もちょっと手元を上げるんですね。
剣先が右斜め上になるような状態、少し自分が面を避けるような状態です。
押してから、相手を押してから、自分が少し避けるような形で手元を上げると、相手が面だと思って避ける動作をするので、その動作のまま引き胴に持っていくという打ち方があります。
これは動画で見た方が分かりやすいと思うので、梶谷彪雅の引き技の動画を検索してみてください。
そういった形で相手を崩して面に見せてからの引き胴というのが有効になります。
パターン②:崩して→引き胴
相手の体勢を崩しての引き胴というのもあります。
ここで大事になるのがやっぱり打ち方の部分です。
自分から見て左側を狙うわけですよね。
相手から見ると右側を狙うんですけど、この一番狭いところ、胴の一番狭いところを狙ってしまうと、外してしまう可能性が高いんです。
引き胴を打つ時の狙いのコツ
狙うのはお腹側です。お腹の方が胴の幅って広いじゃないですか。
お腹すぎると音が鈍くなるんですよ。
真ん中よりもちょっと細いところ、自分から見て左側。
一番左側は細すぎるんで、一番左側とお腹の部分の間ぐらいの部分ですね。
胴の幅が広くなっていくところぐらいを狙うというのが引き胴の打ち方です。
逆胴のテクニック|引き胴と組み合わせる
そしてもう一つが逆胴ですね。
同じく引き面を狙っていたりとか、引き胴を狙っていると、面も胴も隠したいわけですよね。
引き面も引き胴も警戒する。そうすると絶対に逆胴が狙わないんですよ。
逆胴が隙になってきます。三所隠しみたいになってくるんで。
引き胴は、さっき踏み込みということを言いましたが、逆胴の場合は踏み込みいらないんですね。
打突の強さ。
引き胴はどっちかというと音が大事なんですけどね。
音と引く速さというところがものすごく大事になってきます。
逆胴の打ち方①:払って逆胴
引き逆胴の打ち方なんですけど、払って逆胴パターンと、崩して逆胴という、二つのパターンがあるんですよ。
僕の場合は払いが多いですね。自分の左拳で相手の右拳を払います。
そうするとやばいと思って、相手は払われた右拳を元に戻そうとします。
元に戻そうとすると、逆胴が空きやすくなるんですよ。
ぜひやってみてほしいんですけど、払っての逆胴、これは結構効きます。
逆胴の打ち方②:首刈りして逆胴
そして首刈りですね。首刈りをしての逆胴。
この二種類があるので、首刈りの逆胴は相手の体勢を崩して戻る瞬間を狙うという形ですね。
これちょっとパワーがいるんで、僕は払いの方を使っております。

相手を利用する引き胴|試合展開を逆転させる
次に自分から作るんじゃなくて、相手を利用する引き胴を紹介します。
相手を利用する引き胴は二種類あります。
パターン①:間合いを潰してくる相手を利用
つばせり合いの状態で守ろうとしている相手がいるじゃないですか。
守ろうとしている相手ってだいたい間合いを通そうとするんですよ。
打とうとしてくるんですね。
打とうとした時に前に来たりする相手が多いんで、そういう相手を利用する方法は、まず引き面を見せるんです。
そうすると間合いを潰してくるんですよ。
間合いを潰してくる時って、重心が前に来てるんです。
重心が前に来てるから、首刈りをしてみてください。
この時が一番崩れやすいです。
どうしても普通のつばせり合いの状態だと、重心がまっすぐあるので、横に崩れにくいんですよね。
でも危ないと思うと前に来ます。ここが一番崩れやすいんです。
この相手を利用するというのができると、すごくね、崩しとか作りが上手くなるんで、ちょっと理解しながら挑戦してみていただきたいなと思います。
パターン②:すれ違い際の引き胴
そして次にですね、今度引き技がつばせり合いからじゃないパターンですね。
これは僕のね、大学の時の新人戦で、梶谷彪雅vs星子選手が対戦している時だったかな。
あの時に取られたこの引き胴これな気がするので、見てみていただきたいんですが。
僕が面打っていったんですよ。
で振り返り際というか、このすれ違い際みたいなところで、引き胴を打たれたんですよね。
ちょっと一回ね動画見ていただきたいです。
youtubeで「梶谷彪雅新人戦大学」とかで調べると、一番上に出てくると思うんですよ。
その1分45秒ぐらいのところですね。
大将戦の方で星子選手と対戦させていただいて、面を打ってすれ違い際の引き胴。
これはねそう簡単にね試合で打つのって結構難しいと思うんですね。
相手も思い切って技出してきてるわけだからそこに冷静にね、すれ違い際に引き胴を狙う。
これはね素晴らしい技術だなって思います。
でもこれがあるかないかだけで、僕試合展開180度ぐらい変わると思います。
だって相手が惜しい技打ってくるわけですね。
惜しい技打ってきた時に、そのまま終わったら相手ペースになるじゃないですか。
でも振り返り際ですれ違い際で引き技を打たれるってなると、こっちは最後打たれて終わるんですよ。
自分が打ったはずなのに、相手に惜しい技あるいは一本取られるということになるんで、ここはね狙わない方が損だと思います。
ここは正直そこまでスピードいらないと思うんですよね。
相手がどっかに行くから、間合いが自然と切れるんですよ。
相手が前にメーンって打ち切ってくれるんで、自然と間合いを切りやすくなるので、こういったところを狙っていくといいんじゃないかなと思います。
これが相手を利用するタイプの引き胴ですね。
これはコテ抜き面とかそういったものに近いですね。
胴技というとこの試合が一番分かりやすいんじゃないかなと思うので、ぜひ試合見返してみてください。
引き胴の極意|まとめと実践的なポイント
ということで今回はですね、胴打ちの続きとして引き胴についてかなり詳しくですね紹介させていただきました。
引き胴の極意|最重要ポイント
- 大前提:引き胴を打つためにはまず引き面練習しましょう。ここが全ての基礎になります。
- 3つの要素:打突力、踏み込み、下がりの速さが全て揃うことで、一本になります。
- プラスポイント:引き胴は音と引く速さが特に大事です。
- 狙う場所:細いところではなく、胴の幅が広くなっていくところを狙うこと。
- 作り方:引き面をいかに見せれるか。押して見せたり、面を触って見せたり、崩して見せたり、いろいろな方法があります。
- 逆胴の活用:払って逆胴、崩して逆胴も組み合わせましょう。
- 相手を利用する:引き胴の後の崩し、相手が面に来た時のすれ違い際を狙うことで、試合展開を必ず有利に運べます。
なので、まず下がるスピード。ここはね絶対的な練習が必要なので、やりながら技のバリエーション、試合の組み立てを増やしていっていただきたいなと思います。
ぜひ、今日から稽古に引き胴を取り入れて、試合での勝利を掴んでくださいね。
あなたの引き胴が、試合の流れを変える一手になることを願っています。
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?