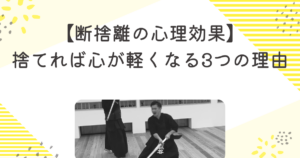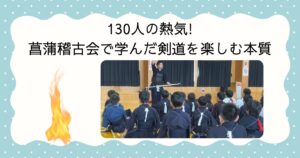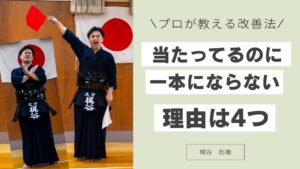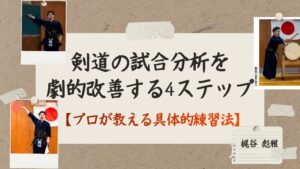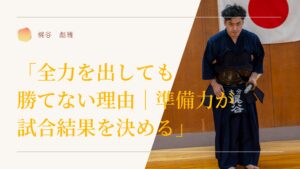剣道で審判批判をやめるべき3つの理由と自責思考の育て方
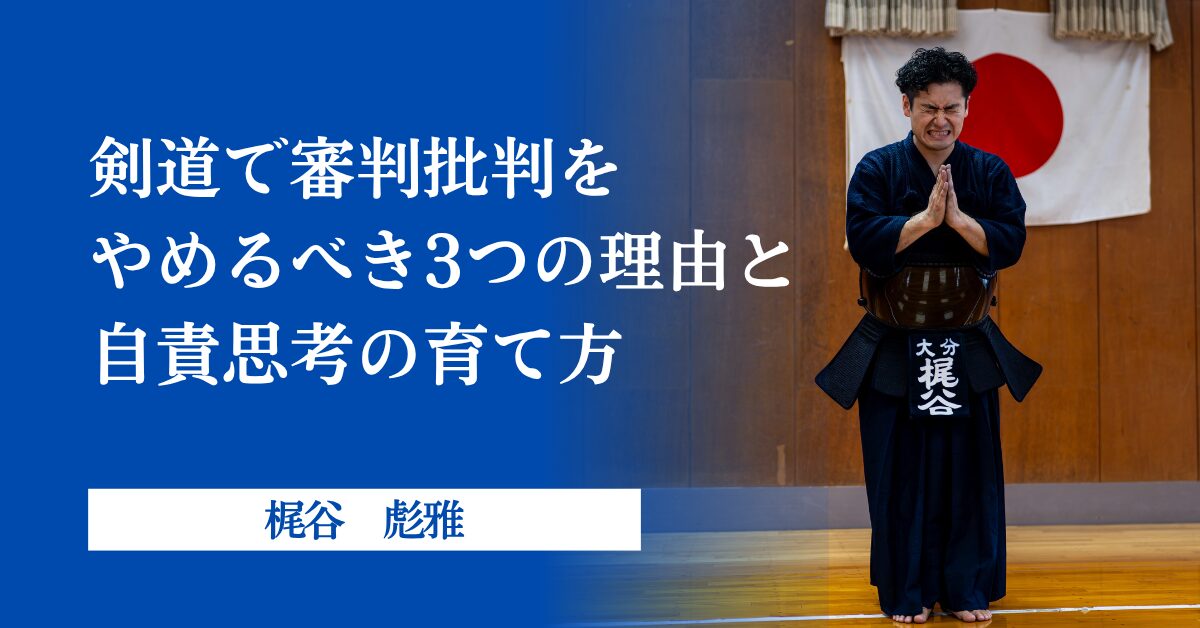


試合で「今の一本、当たってない」って思ったことありませんか?
先日、僕がYouTubeに投稿した国体予選の動画に、「小手が当たってない」というコメントがたくさん届きました。
正直、複雑な気持ちになったんです。
でも結論から言うと、審判批判はやめてください。
本当に、僕が弱いだけなんです。
この記事では、審判批判ではなく自責思考で成長する剣道の本質についてお話しします。

審判批判が意味をなさない理由
有効打突の条件と「見え方」の関係
剣道の有効打突には、こんな条件があります。
「充実した気勢、適正な姿勢を持って、竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心あるもの」
つまり、当たったかどうかだけじゃなくて、どう見えたかも大事なんですよね。
今回の僕の場合、手元を上げてしまったんです。そのいいタイミングで、相手が充実した気勢と適正な姿勢で打ってきた。
だから審判の先生には一本に見えたんです。
これって完全に僕の落ち度なんですよ。当たってる当たってないじゃなくて、僕が打たれるような隙を作ってしまったってことなんです。
剣道にビデオ判定がない理由
もしビデオ判定があって「当たってないからチャレンジできる」っていうルールだったら、当たってる当たってないは大事なポイントになりますよね。
でも剣道ってそういうものじゃないんです。
いいところで打たれたら、旗が上がる可能性は全然あります。逆に、軽くてもいいタイミングだったら一本になることもあるんですよね。
審判の先生も一生懸命やってくださっています。そこに何か言っても、結果は変わらないし、何も生まれないんです。

議論すべきは「なぜ旗が上がったか」
玉竜旗準決勝の旗割れから学ぶ
先日の玉竜旗準決勝、九州学院対日章学園で旗が割れたシーンがありました。
引き胴、引き面で審判の判断が分かれたんです。
先に刃先に当たったのは日章学園の原田選手だったかもしれない。
でも上から乗ったのは九州学院の島村選手だったかもしれない。
充実した姿勢に見えたのは島村選手だったかもしれないし、見る角度によって全然違うんですよね。
ちょうど審判にかぶっていて、僕も見えなかったんですよ。スピードも早くて。
ここで大事なのは、「どっちが悪い」じゃなくて「なぜそう見えたか」を考えることなんです。
自責思考が次の成長につながる
「当たってねえよ」っていうコメントって、どうにもできないじゃないですか。
もう結果で決まっていることに対して言っても、何も変わらないんです。
じゃあ次は手元を上げないようにしよう。もっと入りは慎重に、足さばきや前の攻防を意識しよう。
こういう課題点につなげられるんです。
剣道という武道なので、自分が悪いと考えて、他責にしない。これがものすごく大切なポイントだと思います。

感情表現を抑えるチーム指導の価値
福岡第一に見る理想の態度
最後、福岡第一の新井選手が九州学院の下村選手に小手を取られてしまいました。
がっつり手元が上がったところを打たれたんです。打たれた後に「ああ」ってなりましたよ。
でも監督の藤岡先生が「うんうんうん」って感じでやってて。
その後、新井選手も納得したような、「これは一本だな」って自分に言い聞かせて戻っていたんですよね。
福岡第一の選手すごいのが、相手が一本を取った時も拍手しているんですよ。
こういうチーム指導をするところって、僕は本当にすごいなって思うし、評価されるべきだと思うんです。
東福岡に見る「喜びすぎない」指導
逆の例もあります。
東福岡のいつかの大会で、選手たちが勝ったことによって、めちゃめちゃ盛り上がったんですよ。
会場の中に入っていくんじゃないかっていうぐらい「うわー」ってなってたんです。
その時に監督が、手を差し伸べて、「座ってちゃんと拍手しろ」みたいな、喜びすぎるなっていう指導をしていました。
もちろん一瞬、「おー」とか「面」っていう反応はあっていいと思うんですよ。
盛り上がるし、そういうのもチームの応援としては必要です。
でもやりすぎると良くないんです。負けた時も、やりすぎた悔しがり方をしてしまったり、態度が悪いと、逆に印象を悪くしてしまう可能性があるんですよね。

剣道は心を鍛えていく武道です。ガッツポーズとかも禁止なわけじゃないですか。
こういうふうに指導できる先生の方が、僕はかっこいいなと思います。
日常指導でしか育たない人間性
なかなか僕、講演会とかでそういったチームでそういったところを指導する機会ってないんですよね。
技の技術的な部分は指導できるんですけども、人間性の部分は難しいんです。
喜びすぎるな、悔しさを表現しすぎるな、悔しい気持ちは持てっていうのは言ったりするんですけど、実際その場になってみないとわからないじゃないですか。
嬉しい表情って、やっぱり瞬間的に出ちゃうし。悔しい表情も瞬間的に出ちゃうし。怒りの念も、「はっ」っていうのは瞬間的に僕も出ちゃうことあります。
だからこそ、そういったところを指導できるのは、日頃の練習試合や大会で一緒に同行できる先生が一番指導できるところだと思うんですね。

剣道の自責思考が社会で活きる理由
チーム責任の考え方
この前こんなことがありました。
先鋒の子が一本勝ちして、チームが負けた時に、「お前が二本勝ちしてこないから大将が負けたんだ」みたいなことを大将の子に言われる。
逆に二本勝ちしてきた時も、「お前がもっといい勝ち方をしてこなかったからチームが負けたんだ」みたいなことを言われる。
こんなことを言う子いるの、って思うんですけれども。
やっぱりそういったところをしっかり指導していくことが大事なんです。
責任は全体なのか、大将なのか。どこに責任を置くのか。
「僕が教えられなかった、ちゃんと勝たせてあげられなかった、監督の責任だ。だから誰も責めちゃダメだ。悔しいからみんなでまた一緒に頑張ろう」ってするのか。
ここは監督のいろいろな声かけの仕方があると思うんですけど、やっぱり他責にしないっていう考え方は、ものすごく大切なポイントになってくるんじゃないかな。
社会人でも通じる自責の力
これは剣道だけじゃなくて、社会人になっても大人になっても使える、大切な考え方だと思うんですよ。
仕事で何か失敗した時に、「あいつが悪いから」「あいつが失敗したから俺まで評価下げられちゃった」。
こんなこと言う人を評価しますか。しないですよね。
自分で考えて、自分で行動して結果を残して、それで失敗して「自分が失敗しました、すみません」って言える人の方が成長できると思いませんか。
何か変えていけると思いませんか。
そこをしっかり指導できる先生が増えたらいいなと思います。
今日からあなたも、試合で悔しいことがあったら「審判のせい」じゃなく「自分の何が足りなかったか」を考えてみてください。

まとめ:行動すれば、景色が変わる
- 審判批判ではなく、自分の弱さを認めることが成長の第一歩
- 「なぜ旗が上がったか」を考えることで、次の課題が見えてくる
- 感情をコントロールする力は、剣道だけでなく社会でも一生の財産になる
今日の話が、あなたの一歩を後押しできたら嬉しいです。
剣道は技術だけでなく、人間性を磨く武道です。一緒に成長していきましょう。
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?