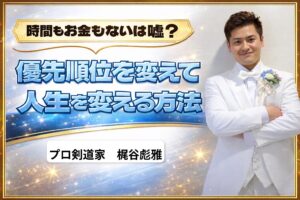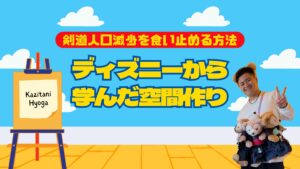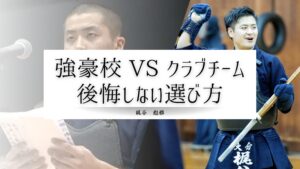ティーチングとコーチング_使い分けで剣道が劇的に上達する方法



ティーチングとコーチング、どちらが重要?
ティーチングとコーチングって聞いて、パッとわかる方もいらっしゃると思いますが、簡単に説明させてください。
ティーチングというのは「あなたはこうしなさい」「こうすれば強くなれるよ」というように、知識やスキルを教えて相手に習得させることです。
一方でコーチングは、どちらかというと導いてあげるイメージですね。相手の成長を促して、自ら答えを見つけられるようにサポートすることです。
先日、「県準優勝から全国制覇まであと一歩までの道のり」という放送でご紹介した九州学院さんのニュース動画に、まさにこのコーチングの本質が映っていました。
監督が「やらされているだけだと本物にはなれないぞ」とおっしゃっていたんです。
これは「こうやれ」「こうすれば日本一になる」というティーチングではなく、選手自身に考えさせるコーチングの姿勢ですよね。
では、この2つのどちらが大切だと思いますか?
今回は梶谷彪雅なりの考えを、皆さんにお伝えしていきたいと思います。
ティーチングとコーチングの違いとは
ティーチング=知識・スキルを教える
ティーチングは、具体的な知識やスキルを教えることです。
たとえば、剣道で言えば「素振りのやり方」「構え方」「足さばき」「面打ちの順序」などを、先生が見本を見せながら教えます。
「こうしなさい」「こうすれば強くなれるよ」と、明確な答えを提示するのがティーチングです。
これは初心者に必須の「地図」のようなものですね。
地図がなければ、どこに向かえばいいのかわかりません。
コーチング=自ら答えを見つけさせる
コーチングは、相手に問いかけて、自ら答えを見つけさせることです。
「どうすればいいと思う?」「なぜ打たれたと思う?」と導いてあげるんです。
九州学院の監督さんが「やらされているだけでは本物にはなれない」とおっしゃっていたのは、まさにこのコーチングの本質ですよね。
指示を待つのではなく、自分で考えて行動する力を育てる。
これは成長を促す「旅」のようなものです。
実際に旅に出なければ、どんな景色が待っているのかわかりませんよね。
どちらが重要か?答えは「どちらも」
僕の考えでは、どちらも重要です。
ただし、順番があるんじゃないかなと思っています。
地図だけでは旅はできません。
でも、旅だけでは迷子になってしまいます。
だから、ティーチングで土台をつくって、コーチングで花を咲かせるという流れが大切だと思うんです。
ティーチングからコーチングへの移行タイミング
初心者はティーチングが8割
基礎知識がない状態では、問いかけが逆に負担になってしまいます。
たとえば、素振りのやり方を全く教えていない初心者の人に対して、「素振りはどういう風にやれば一番早く振れるようになるか考えてください」と言われても、パッと思いつかないと思うんですよ。
だから、初心者にはまずティーチングで土台をつくることが大切です。
構え方、足さばき、面打ちの順序など、全部ティーチングで教えていきます。
これが「守破離」の「守」の段階ですね。
中級者は5:5でバランスを取る
ある程度基礎が固まってきたら、考える力を育てる段階に入ります。
「この場面、どういうふうに攻めた方がいいと思う?」「ここ、なんで今打たれたと思う?」と問いかけるんです。
これがないと、いきなり初心者の人に「なんで梶谷から打たれましたか?」と聞いても、「いや、早かったからです」ぐらいしか答えられないと思うんですよ。
避け方や足さばきが悪いとか、そういったところにも気づかないんです。
これが「守破離」の「破」の段階ですね。
上級者はコーチングが8割
最終的には、自分で考える力が最も大切になります。
試合中は1対1なので、その人が全部自分で判断しないといけませんよね。
だから、上級者になったら、ティーチング2割、コーチング8割ぐらいの割合で指導します。
これが「守破離」の「離」の段階です。
先生の教えから離れて、自分自身で成長していく段階ですね。

よくある失敗パターンと対策
誘導尋問になっていないか?
よくある失敗パターンとしては、自分がティーチングで教えたことをコーチングだと思い込んでるケースがあります。
たとえば、質問しているようで実は誘導尋問みたいな、「これが正しいんだよね?」みたいな感じで押し付けてしまっている。
「いやいや、これ楽しいでしょう」「こういう風にしないといけないよね」「構え崩しちゃダメじゃない」。
これは誘導的にそういう風にしていて、生徒に本来「こうすればいいんじゃないかな」と考えさせていないんです。
コーチングというのは、相手の答えを尊重する勇気が必要になってくるんですね。
たとえ自分の理想の答えと違っても、相手が試行錯誤する過程を認めていく、ここに育成の本質があるんじゃないかなと思っています。
コーチングだけに偏っていないか?
基礎が固まっていないのに、考えさせても答えが出ません。
初心者に「どう打てばいい?」と聞いても、答えられないんです。
だから、段階に応じた指導が必要なんですね。
まずはティーチングで土台をつくって、それからコーチングで花を咲かせる。
この順番が大切です。
ティーチングだけに偏っていないか?
指示ばかりでは、自分で考える力が育たないんです。
「こうしなさい」ばかりでは、試合中に判断できません。
だから、最終的には自分で考える力を育てることが大切なんですね。
ティーチングとコーチング、どちらか一方だけでは不十分です。
バランスが大切なんです。
梶谷彪雅の指導で大切にしていること
ティーチングで土台をつくる
僕が剣道の指導で大切にしているのは、まずはティーチングで土台をつくることです。
たとえば、素振りのやり方を説明して見本を見せて、「こういう風にやれば早く振れますよ」と稽古会で伝えます。
みんな早く振れるようになってきて、形も綺麗になり、音も鳴るようになってきた。
それを毎日100本、200本、300本と続けていくうちに、筋力がついていきます。
これが「地図」を渡す段階ですね。
コーチングで花を咲かせる
ある程度基礎が固まったら、自分で考える力を育てる段階に入ります。
「より一本になるような打ち方をどうすればできるんだろう」「より手の内を効かせるためにはどうすればいいんだろう」と、自分で考え出すんです。
この考えることの重要性を伝えていく、これが僕の考える順番です。
たとえ自分の理想の答えと違っても、相手が試行錯誤する過程を認めていく、ここに育成の本質があるんじゃないかなと思っています。
今後の課題:ティーチングの基礎徹底
僕自身も、この剣道の指導でこのバランスを痛感しています。
最終的には完全に考えさせるところに持っていきたい、自分自身で考えさせるところに持っていきたいのですが、結構ティーチングに偏ってるなというのが、今の僕の指導です。
この前、東北大会があって、プライベートレッスンをしている生徒が2回戦で敗退してしまったんです。
中学生から始めている子なんですが、負けた相手は結果的に優勝しました。
でも、勝ち切れなかった、僕の指導力不足だなと感じました。
もっと本気で勝ちたいと思う人に関しては、ティーチングの基礎能力の徹底を教えていかないと、本当の強さにつながっていかないなと。
まとめ:行動すれば、景色が変わる
- ティーチングとコーチング、どちらも重要。ただし順番がある
- 初心者はティーチング8割、コーチング2割でまずは土台をつくる
- 上級者はティーチング2割、コーチング8割で自ら考える力を育てる
- 相手の段階に応じて使い分けることが、本当の育成につながる
- 誘導尋問にならず、相手の答えを尊重する勇気が必要
ティーチングは「地図」、コーチングは「旅」です。
地図がなければ迷子になり、旅がなければ成長しません。
だから、ティーチングで土台をつくって、コーチングで花を咲かせる。
この順番を意識して、あなたの指導にも取り入れてみてください。
今日の話が、あなたの一歩を後押しできたら嬉しいです。
今日も一生懸命頑張っていきましょう!
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?