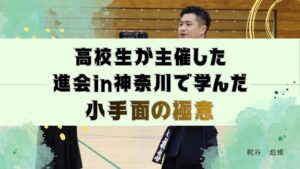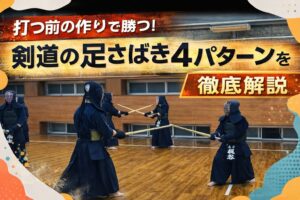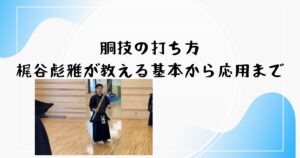【最強スキル】相手から打たれない防御技術の習得法を解説
剣道において攻撃力と同じくらい重要なのが「打たれない技術」です。
どんなに素晴らしい一本を取れても、相手に二本取り返されては勿体無いです。
まるで野球で1回の表に10点取れても、2回の裏に30点取られればチームは負けてしまいます。
今回は、プロ剣道家として剣道の世界普及を目指す梶谷彪雅が監修する「打たれない技術」の完全習得方法を解説します。
この技術をマスターすれば、強豪相手でも負ける確率を大幅に減らすことができるでしょう。

今回の記事で学べること
- 剣道の防御技術と足捌きの基本原理
- 打たれない技術の実践的習得方法
- 絶対防御を構築するための3つの要素
読者対象
- 防御技術向上:相手からよく一本を取られてしまう剣道家
- 足捌き改善:重要な場面で足が止まってしまう競技者
- 試合対策:強豪相手との対戦で勝率を上げたい剣士

相手から打たれてしまう3つの根本原因
まず、なぜ相手から一本を取られてしまうのか、その原因を明確にしましょう。
打たれる原因は「足」「手」「思考」の3つの要素に分けることができます。
原因①:重要な場面で足が止まってしまう
「足が止まる」と聞くと、常に動き回る必要があると勘違いしがちですが、これは間違いです。
大切なのは「重要な場面(打たれる場面)で足が止まらない」ことです。
高段者の先生方を見てください。常に動き回っているわけではありませんが、一本を取るのは非常に困難です。
なぜなら「重要な場面を理解し、その瞬間に適切に対応できる」からです。
打たれる場面として特に注意すべきは:
- 入り際(打突できる間合いに入る瞬間)
- 別れ際(近間から離れていく瞬間)
- 下がった後(攻め合い・前技・引き技の後)
- 「危ない!」と思った後(びっくりした後の油断)
原因②:竹刀を使った避け方が甘い
手元を上げて面を避けたり、竹刀で相手の攻撃を阻止する技術は重要ですが、「避けていると勘違いする」ことが最も危険です。
典型的な例として:
- しっかり手元を上げているのに面を乗られる
- 手元を隠しているのに下から小手を差し込まれる
- 三所隠しをしているが、逆胴が空いている
竹刀だけの防御には必ず隙があります。
打たれる確率を減らすことはできても、「絶対防御」は困難なのです。
原因③:相手を攻めることができていない
防御とは足や竹刀で避けるだけではありません。「攻撃することで相手に技を出させない方法」も重要な防御の一つです。
例えば、相手が面技を得意とする選手なら、小手技や胴技を狙い続けることで、相手は面を打てなくなります。
面技しか打てない選手は、負けるのが怖くて技を出せなくなるでしょう。
このように「技の方程式」を理解し、相手の得意技に対する応じ技を身につけることで、攻撃が防御に変わるのです。
こんな相手にはこんな技の選択があるよね。というのを全てまとめています!
絶対にやってはいけない3つのNG行動
打たれない技術を向上させるために、絶対に避けるべき行動があります。
これらを一つでも行うと、負ける確率が大幅に高まります。

NG行動①:重要な場面で足が動かない
前述の4つの「打たれる場面」で足が止まることは致命的です。
特に、
- 入り際:試合後半の集中力切れに要注意
- 別れ際:鍔迫り合い解消時の隙を狙われる
- 下がる場面:攻め合い・前技・引き技後の油断
- びっくり後:「ホッ」とした瞬間の集中力低下
手だけ(竹刀だけ)で避けようとすると、必ずどこかに隙が生まれます:
NG行動②:手だけ・足だけで避ける
面を隠す → 小手や胴に隙
小手を隠す → 面に隙
三所隠し → 逆胴・突きに隙
逆胴を隠す → 面・小手・突きに隙
どこかを隠せば、必ずどこかに隙ができるのが竹刀だけの防御の限界です。
NG行動③:相手の動きを見て避ける
強い選手はフェイントを多用します。相手の技を見て反応するには限界があり、
「予測」することが重要です。
結論として:重要な場面で手だけで避けず、手・足の両方を使い、相手の技を見ずに予測して避けることが「打たれない技術」の核心です。
打たれない技術習得のための3つの実践方法
では具体的に何を練習すれば良いのでしょうか?打たれない技術習得のための実践方法を3つ紹介します。
実践方法①:常に動ける足捌きの習得
重要な場面で足が止まらないためには「いつでも動ける足捌き」を身につける必要があります。
私が常に意識している方法は「完全に止まらない」ことです。
具体的には:
- 前に蹴りながら、後ろに蹴るを同時に常に行う
- 大きな足捌きは逆効果。小刻みな移動を心がける
- 相手の動き出しの瞬間に「前後」どちらにでも移動できる状態を作る
間合いによる判断基準:
- 相手が打てる間合い → 絶対に下がらず前で捌く
- 相手が打てない間合い → 後ろに下がってもOK
実践方法②:手元・竹刀を使った避け方の練習
足捌きを極めた後は、手元の使い方・竹刀での避け方をマスターします。
間合いに入った後に足だけで捌くのは限界があるからです。
主な避け方の種類:
- 手元を上げて避ける方法(剣先の向きで面を隠す部分が変化)
- 手元を前に出して避ける方法(右側・左側への避け方)
- 竹刀の剣先を右に向けて小手を隠す
- 構えた状態で突き止めをする
実践を交えた練習方法が最も効果的です:
- 攻撃vs防御の練習:10-30秒で時間を区切り、役割を分けて練習
- 練習試合での守る練習:強豪校との対戦で防御を徹底する
実践方法③:スピード・打突力・踏み込みの強化
これらの強化により「本当の攻め」に近づけることができます。
攻めとは「相手の心を動かすこと」であり、一本に必要な要素が弱ければ相手は怖がりません。
技の打ち方や種類を覚えるよりも、本質的に重要なのは「一本に必要な筋力強化」です。
竹刀を扱えるパワーがなければ、技術だけでは効果は低いのです。
継続的なトレーニングと習慣化が重要であり、明確な目標設定が継続力を高める鍵となります。

まとめ:絶対防御で勝率を劇的に向上させる方法
今回解説した「打たれない技術」をマスターできれば、負ける確率を大幅に減らすことができます。
打たれない=負けないということは、個人戦なら優勝が確定し、団体戦でも必ずチャンスが生まれます。
メリット
- 防御力向上:相手からの攻撃を効果的に回避できる
- 勝率アップ:強豪相手でも負ける確率を大幅に削減
- 精神的余裕:守れる自信が攻撃のチャンス創出につながる
- 技術の向上:相手を見切る力と予測能力が身につく
デメリット
- 習得時間:完全な技術習得には長期間の継続練習が必要
- 体力消耗:常に集中を保つため精神的・体力的負担が大きい
- 判断力要求:瞬時の状況判断能力が求められる
100%の絶対防御を作り出すのは困難ですが、近づけることは必ずできます。
諦めずに負けない技術習得に向けて努力を続けましょう。
強い相手に負けなくなると、剣道がさらに楽しくなり、そして勝てるようになったときの喜びは格別です。
今すぐ実践してください:
- 今週は「足が止まらない練習」を重点的に行う
- 来週は「避け方の練習」に集中する
- 継続的な基礎体力・筋力トレーニングを開始する
夢や目標達成に向けて、一緒に頑張っていきましょう!
日本一の経験をすぐに聞ける環境に!
あなたの剣道を変える。
剣道で本当に強くなりたいですか?
梶谷彪雅が あなたの試合を個別分析 し、具体的な改善点を直接アドバイスします!
📊 2つのメンバーシップ
- 梶谷による個別試合分析
- 限定チャット参加権
- 日々の成長を共有する「剣道ノート部屋」
- 限定映像・活動報告
- 剣道普及活動への応援
- 限定映像・活動報告
⏰ なぜ今すぐ参加すべきか
現役生の練習時間は限られています。
何を直せばいいか分からない稽古を続けますか?
それとも日本一の視点で課題を明確にし、確実に成長しますか?
「昨日の自分を超える」仲間と一緒に、本気で剣道に向き合いませんか?